中学受験を目指すお子さんを持つ多くの保護者の方が、「合格するためには、どれくらい勉強させればいいのだろうか」という疑問をお持ちでしょう。ただ長時間机に向かうだけでは、効率が悪く、お子さんの負担になるばかりです。
この記事では、中学受験に合格するために必要な勉強時間の目安から、その時間を最大限に活かすための効率的な学習方法、さらには保護者の方のサポート方法まで詳しく解説します。
中学受験に必要な勉強時間の全体像
中学受験の総勉強時間の目安はどのくらいですか?
中学受験に合格するために必要とされる総勉強時間は、3年間(小学4年生から6年生)で約2,000〜3,000時間が目安とされています。これは、志望校のレベルや元々の学力によって変動する数値ですが、この膨大な時間をいかに計画的に積み重ねていくかが合否を分けます。
この時間を3年間で単純に割ると、年間約700〜1,000時間、月平均で60〜80時間、1日あたり2〜3時間の勉強が必要になる計算です。もちろん、学年が上がるごとに勉強時間は増えていきます。
学年別の勉強時間の平均と目安は?
中学受験における学習時間は、学年が上がるにつれて増加します。一般的な目安としては、以下のようになります。
- 小学4年生: 平日1〜2時間、休日2〜3時間。この時期は勉強習慣を身につけることが最優先です。
- 小学5年生: 平日2〜3時間、休日4〜6時間。学習内容が本格化し、量と難易度が急増するため、勉強時間が大幅に増えます。
- 小学6年生: 平日3〜5時間、休日8〜10時間。受験直前期には、塾の授業時間も含めて、平日で5時間前後、休日には12時間以上勉強することもあります。
合格した小学生へのアンケート調査では、小学6年生の平日の平均学習時間は「3〜5時間」が最も多く、塾の授業時間以外にも自宅や自習室で勉強していることがわかっています。

うちは、小学校5年生の終わりから中学受験の勉強を始めたので、とてもハードでした。そもそもみんなが4年生くらいからは勉強を始めてコツコツと勉強時間を積み上げていることを考えると、小学校5年生の終わりから約1年間で受験勉強をして成果を出すには、よほど自頭が良い子でないと不可能な気がしました。
今の小学生は大変ですが、もし中学受験を目指すなら、遅くとも5年生の最初くらいの時期には始めないときつかった、といったのが実感です(それでも周りと比べると遅いかもしれませんが、ギリギリ追いつけるタイミングでしょうか)。
志望校のレベル別に勉強時間はどう変わりますか?
志望校のレベルが高くなるほど、必要な勉強時間は長くなる傾向にあります。
- 中堅校: 平日3〜4時間、休日5〜6時間程度でも、効率の良い学習ができれば合格は可能です。
- 難関校(偏差値60以上): 平日4〜5時間、休日8〜10時間以上が目安となります。出題範囲が広く、特殊な内容も含まれるため、その対策に多くの時間が必要です。
- 御三家・最難関校(偏差値70以上): 小学6年生の夏休み以降は、1日10時間以上の勉強時間を確保するお子さんも珍しくありません。トップ層では、膨大な学習量をこなすことが当たり前となっています。
ただし、重要なのは勉強の量だけでなく、質にもこだわることです。長時間机に向かっていても、集中力がなければ意味がありません。
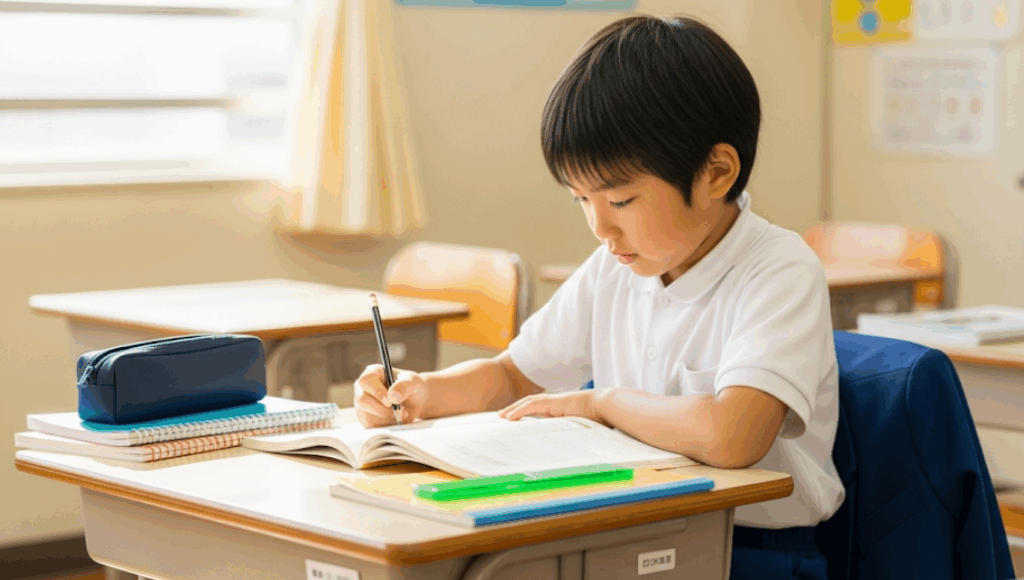
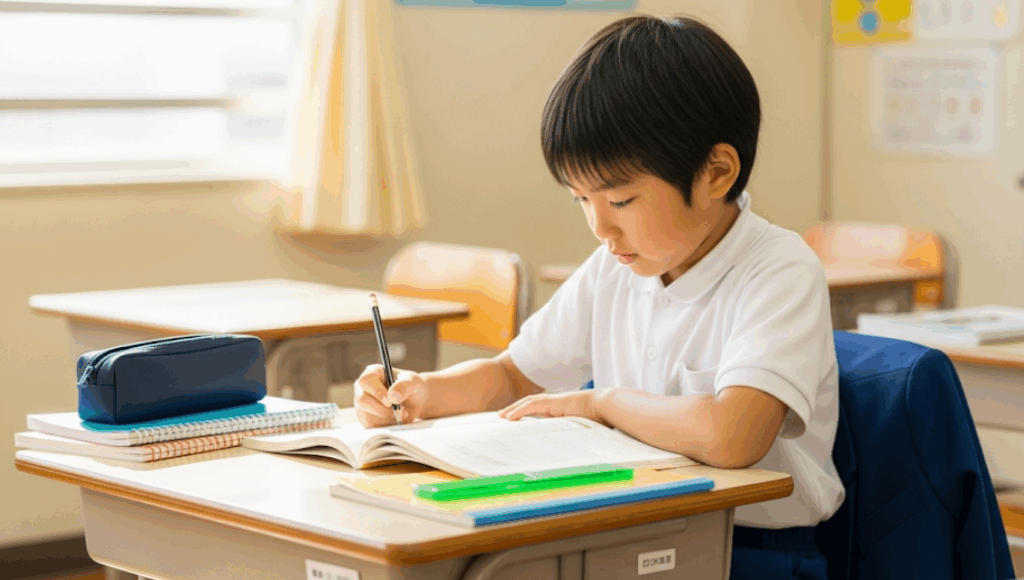
学年別の勉強時間の目安と学習のポイント
小4(4年生)の勉強時間の目安と学習習慣の作り方は?
小学4年生は、中学受験の勉強を本格的にスタートする時期です。この時期の勉強時間は、平日1〜2時間、休日2〜3時間が目安となります。
この時期の最も大切な目標は、勉強を毎日続ける習慣を身につけることです。
いきなり長時間の勉強を課すのではなく、1日30分からでも良いので、机に向かう練習から始めましょう。子どもたちの集中力は短いため、「20分勉強して5分休憩」といったポモドーロ・テクニックなどを活用するのも効果的です。勉強時間を少しずつ伸ばしていくことで、長時間勉強にも慣れやすくなります。



うちは、小学校4年生は、勉強をしていなかったのですが、確かにこのころから勉強習慣をつけておくと後が楽になるのはその通りだと感じます。
小5(5年生)の勉強時間はどのくらい?学習量が増えたときの乗り越え方は?
小学5年生になると、受験勉強が本格化し、学習量と難易度が急増します。この時期の勉強時間は、平日2〜3時間、休日4〜5時間が目安です。
この時期に多くの生徒が壁にぶつかります。
塾の課題が多くて終わらない、他の習い事との両立が難しい、といった悩みが顕著になります。乗り越えるためには、まず基礎学力を高めることが重要です。計算や漢字など、基礎的な部分は隙間時間を使ってでも毎日コツコツと取り組みましょう。
また、睡眠時間を確保することも非常に大切です。睡眠不足は集中力や記憶力の低下を招き、勉強効率を悪くします。勉強時間を確保するために無理に睡眠時間を削ることは避けるべきです。
小6(6年生)の勉強時間はどのくらい?受験直前期の過ごし方は?
受験本番を迎える小学6年生は、勉強時間が大幅に増加します。この時期の勉強時間は、平日3〜5時間、休日8〜10時間が目安です。
特に夏休みは、学力を大きく伸ばす絶好の機会です。
塾の夏期講習や自習時間を含め、1日12時間以上勉強するお子さんも珍しくありません。受験直前期には、体調管理が最優先となります。無理な勉強は体調を崩す原因になるため、普段通りの生活を心がけ、早寝早起きを徹底しましょう。睡眠時間を削ってまで勉強するのは非効率です。
この時期は、過去問演習に本格的に取り組み、本番の時間配分に慣れることが重要です。



小学校6年生の夏休みは、ほんとうに勉強漬けです・・・。
(見ていていてかわいそうになりましたが)


勉強時間を確保するための具体的な方法
塾の有無で勉強時間はどう変わりますか?(塾あり・塾なし)
中学受験では、多くの家庭が進学塾を利用します。
塾に通う場合は、塾の授業時間(インプット)に加えて、家庭での宿題や復習(アウトプット)の時間を確保することが不可欠です。塾のある日は帰宅後の勉強時間が限られるため、朝の時間を活用するなど工夫が必要です。
一方、塾に通わず独学で受験に挑む場合は、親のサポートが不可欠です。
教材選び、学習計画の作成、進捗管理など、親が主体となって進めることになります。このスタイルは、子どものペースに合わせやすいメリットがある反面、最新の受験情報収集や学習の継続性を保つのが難しいというデメリットもあります。



多くの子ども塾に行くと思いますが、受験勉強の開始が遅れると、塾に入ることすらできなくなるので要注意です。
うちは、小学校5年生の終わりから始めたので、進学塾については入れる塾はありませんでした(そもそも学力的に習っていないことだらけだったので)。
塾に実際に通うかどうかは別として、進学塾の検討自体は小学校4年生くらいにはしておくべきだったと後悔しています。
習い事と勉強を両立させるための時間の使い方は?
小学5年生頃になると、習い事を続けるかどうかの判断に迫られるご家庭も多いでしょう。習い事は気分転換にもなるため、無理にすべてやめる必要はありません。
両立のポイントは、空き時間を「見える化」することです。
平日や週末のスケジュールを書き出し、どこに勉強時間を確保できるかを確認しましょう。短い隙間時間には暗記系の学習を、まとまった時間には演習問題に取り組むなど、メリハリをつけることが大切です。
効率的なスケジュールを立てるにはどうすればいいですか?
スケジュールを立てる際は、「〇時間勉強する」という目標だけでなく、「その時間で何をできるようにするか」という内容をセットにするのが効果的です。
- やるべき勉強量を決める: 1日にやるべき宿題や復習の量を具体的に決めます。
- 時間を設定する: 決めた内容を終わらせるのにかかる時間を予想し、タイマーで時間を区切って取り組みます。
- 予備日を作る: 計画通りにいかないことを前提に、1週間に1日程度、やり残したことに取り組む予備日を設定しておくと安心です。
隙間時間を活用した効果的な勉強法とは?
通塾の移動中や休憩時間など、短時間でもできる勉強をあらかじめ決めておくと、時間を無駄にすることなく有効活用できます。隙間時間には、まとまった時間を必要としない暗記系の勉強が特におすすめです。
- 暗記カード: 歴史の年号や社会の用語、理科の公式などをまとめたカードを持ち歩く。
- 計算練習: 毎朝10分だけでも計算ドリルに取り組む。
- 音読: 国語の文章や社会の教科書を声に出して読む。
これらの小さな積み重ねが、大きな成果につながります。
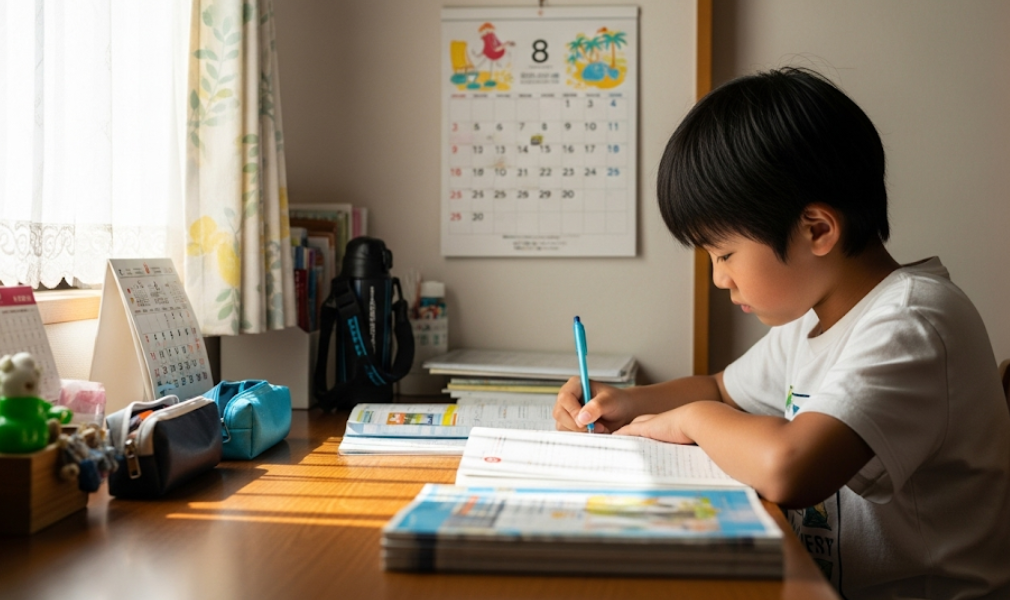
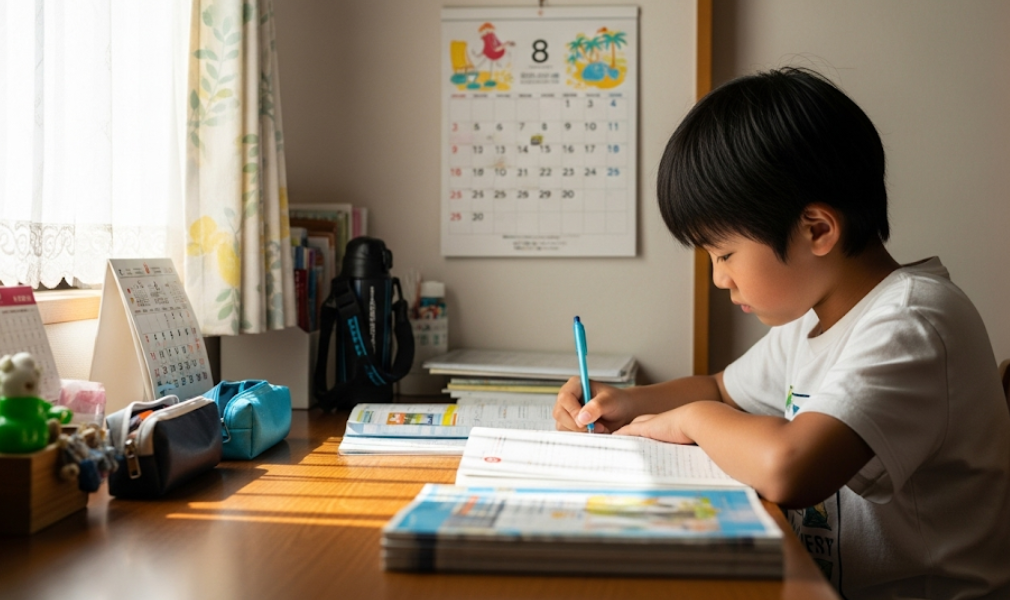
勉強の「質」を高めるためのコツ
量より質が重要って本当?勉強の質を高めるには?
中学受験において、勉強の「量」だけでなく「質」が非常に重要であることは事実です。長時間机に向かっていても、ただ時間を消費しているだけでは学力は向上しません。
勉強の質を高めるためには、以下の3つを意識しましょう。
- 集中すること: 勉強中は気が散るものを遠ざけ、目の前の課題に没頭できる環境を整えます。
- 内容を理解すること: 問題を解いて終わりではなく、「なぜその答えになるのか」を自分の言葉で説明できるまで深く理解します。
- 復習をすること: 人は覚えたことの半分以上を1日で忘れてしまいます。習った内容をすぐに復習し、記憶を定着させることが大切です。



確かに理想としては「量ではなく質が重要」なのはわかるのですが、中学受験は圧倒的な勉強量が降ってくるので、質を意識したり、ゆっくり内容を理解したりするのに時間を費やすのは難しい気はしています。
集中力を維持するための時間管理術とは?
小学生の集中力は長く続きません。
そのため、時間を区切って休憩を挟むことが集中力維持に効果的です。
- ポモドーロ・テクニック: 「25分勉強+5分休憩」のサイクルを繰り返します。小学6年生になったら、試験時間に合わせた「45分勉強+10分休憩」なども試してみましょう。
- 休憩の取り方: 休憩中は、立ち上がって体を動かしたり、深呼吸をしたりして、脳をリフレッシュさせましょう。ゲームや動画など、集中力を奪うものは避けるべきです。
- 朝の活用: 起床後3時間は、脳の「ゴールデンタイム」と言われ、集中力が高まりやすい時間帯です。思考力が必要な算数や国語の勉強に取り組むのがおすすめです。
科目別の理想的な勉強時間の配分を教えてください
お子さんの得意・不得意によって配分は異なりますが、一般的に算数に最も多くの時間を割くべきとされています。算数は入試で最も差がつきやすく、演習量が必要な科目だからです。
- 算数: 勉強時間の約40%を占めるように配分します。
- 国語: 読解力と語彙力を高めるため、約30%の時間を確保しましょう。
- 理科・社会: 暗記が中心となるため、隙間時間も活用して効率的に学習します。両科目合わせて約30%が目安です。
復習のタイミングはいつがベスト?
復習は、勉強した直後に行うのが最も効果的です。
塾や学校で習った内容は、その日のうちに復習する習慣をつけましょう。
塾から帰宅するのが遅くなる場合は、翌朝早く起きて復習に取り組むのも良い方法です。復習をすぐに行うことで、記憶の定着が格段に高まり、勉強効率が上がります。
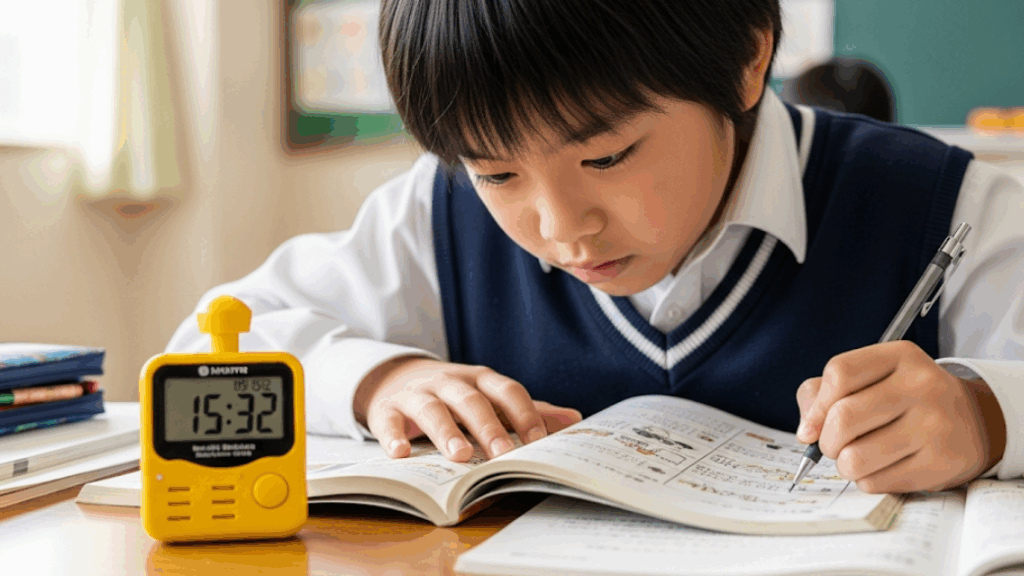
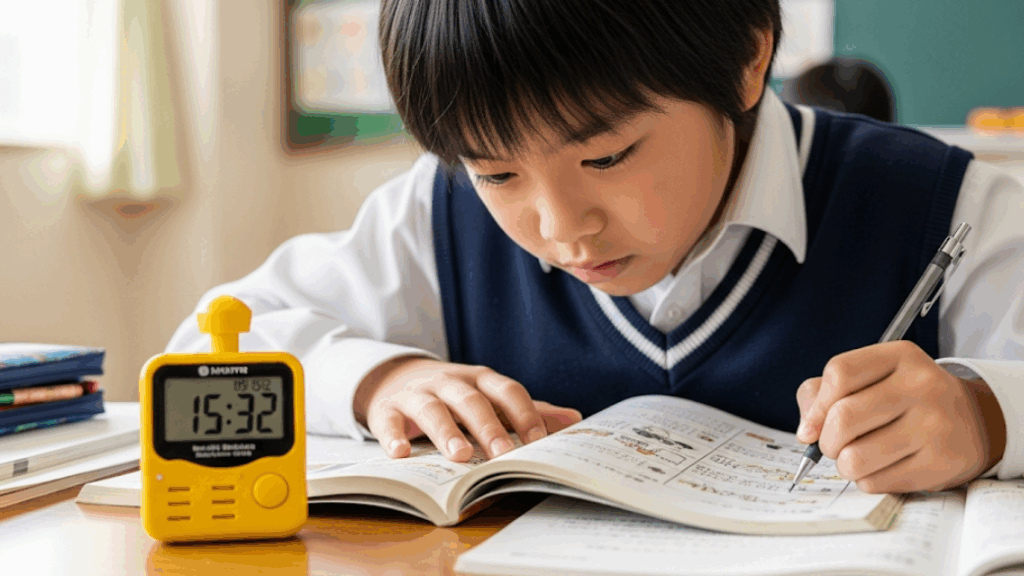
勉強の悩みと解決策
勉強時間が足りないと感じたときにどうすべきですか?
勉強時間が足りないと感じたときは、むやみに時間を増やすのではなく、まずは勉強の「質」を見直すことが重要です。長時間だらだら勉強していないか、復習がおろそかになっていないかを確認しましょう。
それでも足りない場合は、スケジュールの見直しをします。無駄な時間を特定し、隙間時間を活用したり、朝型の生活に切り替えたりするなど、効率的に時間を作り出す工夫をしましょう。



やることが多すぎて、質を見直すこと自体が難しいのが実情だと思います。
個人的には、圧倒的な量が降ってくるので「どこを捨てるか」を決断する勇気が一番重要な気がしました。
捨てるのも勇気がいりますが、そうしないと「質」を意識できないですね。
睡眠時間を削っても大丈夫?適切な睡眠時間は?
睡眠時間を削って勉強するのは絶対に避けるべきです。 小学生の体と心は成長段階にあり、十分な睡眠が不可欠です。睡眠不足は集中力や記憶力の低下を招くだけでなく、体調不良や発育阻害の原因にもなります。
小学6年生でも、最低でも6時間、理想は8時間の睡眠を確保しましょう。夜遅くまで勉強するよりも、早めに寝て翌朝早く起きて勉強するほうが、はるかに効率的です。
親はどこまで勉強に関わるべきですか?効果的なサポート方法は?
親は、お子さんの「勉強を管理する人」ではなく、「良き伴走者」としてサポートに徹することが理想的です。過干渉は、お子さんの自立心やモチベーションを奪う原因になります。
効果的なサポート方法とは、以下の4つです。
- 生活習慣の管理: 規則正しい生活リズムを保てるよう、食事や睡眠の時間を管理します。
- 集中できる環境づくり: 気が散るものを片付け、勉強に集中できる空間を提供します。
- 声かけ: 勉強の進捗だけでなく、悩みや不安な気持ちにも耳を傾け、「頑張っているね」「次があるよ」と励ましましょう。
- 結果に一喜一憂しない: 模試やテストの結果だけで判断せず、努力の過程を認め、次の目標を一緒に考えましょう。
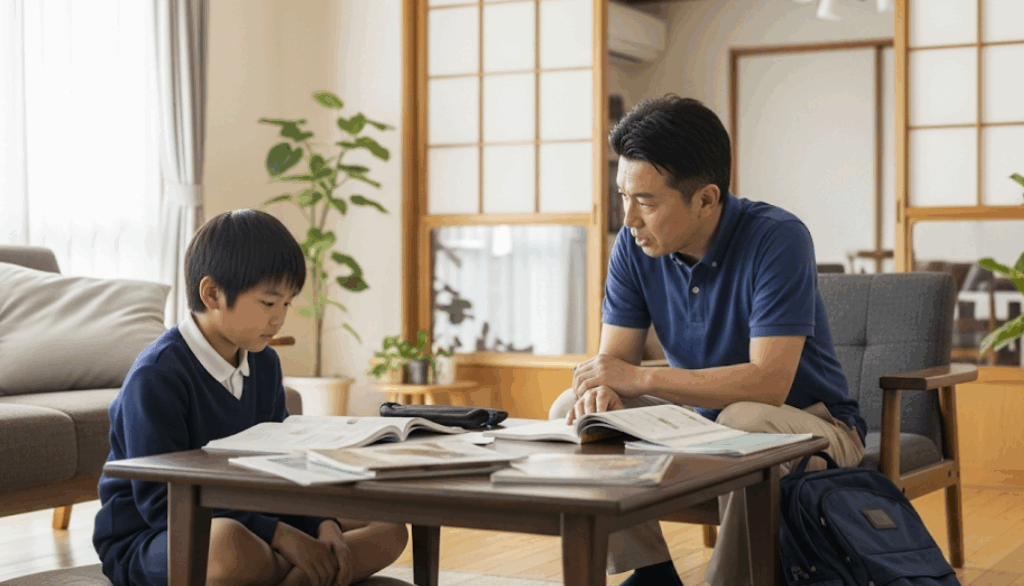
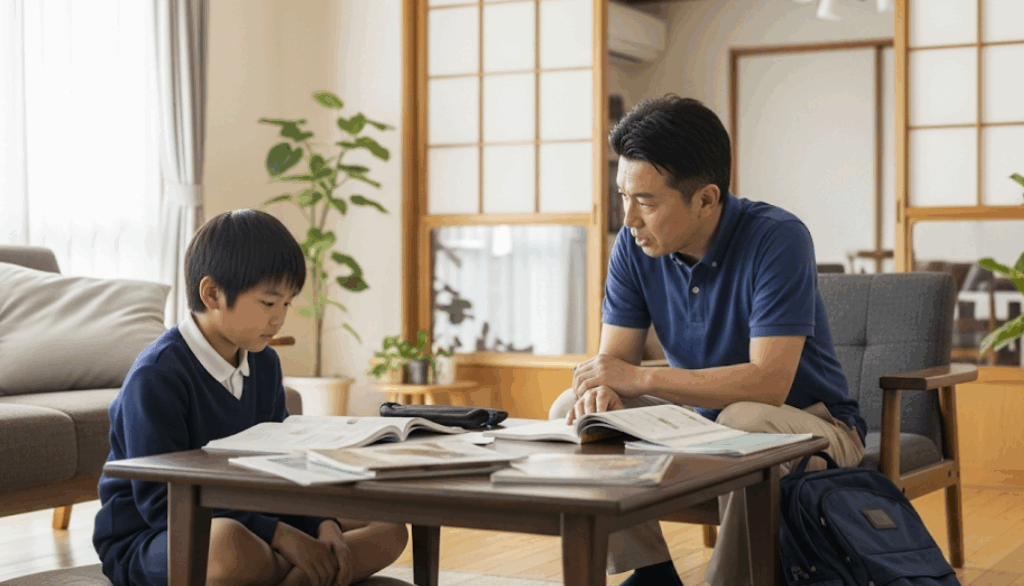
勉強しても成績が伸びない原因と対策は?
時間をかけて勉強しているのに成績が上がらない場合、「わかる」と「できる」の間にギャップがある可能性があります。
考えられる原因と対策は以下の通りです。
- 原因: 問題を解いて終わり、解説を読んだだけで理解したつもりになっている。
- 対策: 解けなかった問題は必ず解き直し、「なぜ間違えたのか」を分析し、自分の言葉で解説できるまで深く理解する習慣をつけましょう。
- 原因: 苦手科目を避け、得意科目ばかり勉強している。
- 対策: 成績の伸びしろが大きいのは苦手科目です。苦手科目には、時間を短めに設定して頻度を増やすなど、工夫して取り組みましょう。
- 原因: 勉強のやり方が自分に合っていない。
- 対策: 親子で話し合い、様々な勉強法を試してみましょう。塾の先生や家庭教師に相談するのも有効です。


コメント