小学校で不登校を経験したお子さんが、中学受験に挑戦することはできるのでしょうか?応募資格に制限はあるのか、受験で不利に扱われることはあるのか――不安に思う保護者の方も多いでしょう。
本記事では、私立中学校や国公立の中高一貫校(国立大学附属中学・公立中等教育学校など)への中学受験について、不登校経験が与える影響を整理します。
不登校の子が中学受験を選ぶ理由やメリット(地元の公立中学に進みづらい事情がある場合など)、学校側の配慮・サポート体制、そして実際の合格実績・成功例まで、保護者が参考にできる情報を網羅的にまとめました。
結論から言えば、小学校で不登校だった子どもでも中学受験は十分可能です。
その理由とポイントを、順を追って解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
不登校でも中学受験は可能です
まず結論ですが、たとえ小学校で不登校でも中学受験は可能です。
不登校だったこと自体が法律上の出願資格に抵触することはなく、学齢相当であれば私立中学校や中高一貫校の入試を受けることに制限はありません。実際、環境を変えるために中学受験に挑戦する不登校の小学生は決して珍しくなく、一定数存在します。
文部科学省の協議会においても「中学受験生の中には小学校時代に不登校になった子が交じっている」事実が報告されています。つまり、不登校経験があっても中学受験に挑戦する子どもは全国的にみられるのです。
中学受験の選抜方法自体が、不登校の子に門戸を開いています。
多くの中学校(特に私立)は入試の学力試験によって合否を決めており、極端な場合を除いて在籍小学校での出席日数や内申(成績評価)が合否に直接影響することはほとんどありません。実際、教育専門メディアも「不登校からの中学受験は一部の学校を除けば周りの受験生と同じスタートラインで挑戦でき、不登校だから合格できないということはない」と断言しています。
ある中学受験塾の調査によれば、首都圏では約7割の私立中学校が不登校経験のある児童でも合格・入学が可能であり、当日の試験結果さえ良ければ合否には不登校かどうかは関係ないケースが大半です。こうした理由から、小学校で不登校だったお子さんでも中学受験を通じて新たな学校に進むことは十分に可能と言えるでしょう。

私立中学校の場合:学力試験が中心で出席状況は重視されない
私立中学校の入試では、基本的に学力試験の成績が合否を決めます。
多くの私立校では小学校の成績表や出欠状況は参考程度で、提出を求めないか、提出してもほとんど評価しないことが一般的です。そのため、小学校で不登校だったことが私立中学入試においてハンデになる可能性は低いと考えられます。
実際、専門家も「中学受験は本当に当日のペーパーテスト(学力試験)の得点で決まります。点数さえ高ければ確実に合格に近づき、不必要に調査書の内容に神経質になるより得点を上げることの方が大切」と述べています。私立中の大半は「試験一発勝負」で、公平に学力のみを見る学校が多いのです。
ただし、一部の難関私立中学では例外もあります。
学校によっては出願時に小学校の通知表のコピー提出を求めたり、調査書(報告書)に小学時代の成績・所見が記載され、それを点数化して合否判定に加味するケースもゼロではありません。とはいえ、そのような学校は限られており、中堅レベルまでの私立中学なら調査書不要の所がほとんどというのが現状です。
実際、ある地域では「通知表(調査書)なしで受験できる私立校」と「調査書ありで出席日数や所見まで求める私立校」が両方存在し、不登校の場合は前者の学校を選ぶことで特に問題なく受験できたという声もあります。不登校のお子さんが私立中学を受験する際は、調査書提出が不要な学校を選ぶことで基本的に不利なく挑戦可能と言えるでしょう。
また、私立中学では入試時に保護者同伴の面接や本人面接を課す学校もあります。面接がある場合でも、不登校の経緯が直接の減点になることは通常ありません。
ただし質問の中で「小学校を休みがちだった理由」などを聞かれる可能性はあります。その際は正直に事情を説明し、中学から心機一転頑張りたい意欲を伝えることが大切です。学校側も、そこで前向きな姿勢が見られれば理解を示してくれるでしょう。

公立中高一貫校・国立中学校の場合:調査書や出席日数に留意
公立の中高一貫校(公立中等教育学校や中高一貫型の県立・市立中学校)や国立大学附属中学校の入試では、小学校から提出される調査書(報告書)が選考に用いられる点に注意が必要です。
これらの学校では適性検査(学力検査)と調査書の両方を組み合わせて合否判定を行うことが多く、私立とは選考方法が異なります。学校にもよりますが、配点比率の一例として「適性検査:調査書=8:2」程度で調査書点を加えるケースも報告されています。
実際、筑波大学附属駒場中学校の募集要項では「国語・社会・算数・理科の学力検査(各100点、計400点)+報告書100点」で合否を決定すると明記されています。つまり、公立中高一貫校・国立中では小学校での成績や出欠状況が一定の評価対象になりうるのです。
では、不登校だった場合その調査書は不利に働くのでしょうか?
結論から言うと、合否への影響はケースバイケースですが、欠席日数が極端に多い場合には注意が必要です。例えば年間数日の欠席であれば問題視されないことが多い一方、半年以上に及ぶ長期欠席となると「合格しても通学できるか?」と学校側が心配し、同じ学力なら出席状況の良い子を優先したいと考える可能性は否定できません。実際、適性検査で競り合った際の参考として長期欠席が合否判断に影響する場合もありえます。
とはいえ、これも学校によります。
近年はコロナ禍の影響もあり「体調不良時は無理に登校しない方が良い」という風潮から欠席に寛容な考え方が広まっており、多少の欠席日数は合否に影響しにくくなっているとの指摘もあります実際、多くの中高一貫校では欠席日数より当日の適性検査成績を重視しており、不登校だった子でも高得点を取れば合格可能です。
不登校のお子さんが公立中高一貫校や国立中を受験する際のポイントは以下のとおりです。
事前に小学校や志望校へ相談する
在籍小学校には「◯◯中学の受験を考えている」ことを早めに伝えましょう。調査書の作成時にできる限り配慮してもらえますし、過去の成績や所見欄で強みが出るよう協力してくれる場合もあります。
また志望校にも、不安な点は直接問い合わせて構いません。「欠席日数は合否にどう影響しますか」「過去に不登校経験者の合格例はありますか」など、気になることは事前に確認しておくと安心です。学校側も問い合わせには丁寧に答えてくれるはずです。
「出席扱い」制度を活用する
現在不登校が続いている場合、自治体の適応指導教室やフリースクールに通うことで小学校での出席日数にカウントしてもらえる制度があります。昨今はこの制度を利用して欠席日数をカバーするケースが増えています。
可能であれば小学校と相談し、別室登校・フリースクール利用などで形式上の欠席日数を減らしておくことも一つの戦略です。調査書上の欠席が少なくなることで、合否判断上の不安材料を減らせます。
それでも重要なのは当日の実力
調査書を課す学校とはいえ、中学入試でもっとも重視されるのは当日の試験結果です。
調査書が必要な公立・国立志望の場合でも、小学校での内申点を気に病みすぎるより、適性検査対策に力を注いで点数を伸ばすことが合格への近道となります。過去には小学校で長期欠席し通知表がオール「C」評価だった子が、公立中高一貫校の適性検査で満点近く取り合格した例もあります。最後はお子さんの実力勝負ですから、過度に萎縮せず挑戦しましょう。
不登校だったことで受験に不利になることはある?
前述のとおり、大半の中学校では不登校経験それ自体が合否を左右することはほぼありません。中学受験は当日の学力試験で決まる色合いが濃く、「不登校=落ちる」という心配は不要です。事実、首都圏の私立中学の場合「不登校だったから不合格になった」というケースは基本的になく、同じスタートラインで受験に挑めます。
あるプロ家庭教師の調査でも「都内私立の約7割は不登校でも合格・入学が可能」であり、入試当日の得点さえ取れれば問題ない学校が多数派であると報告されています。このように制度上・選考上は不登校が大きなハンデにならないのが中学受験の特徴です。
ただし、いくつか留意すべきポイントもあります。
学校により欠席日数への姿勢が異なる
前述のように、公立中高一貫校など一部では長期欠席があると合否判定で慎重になる場合があります。また私立校でも、入学後の出席を不安視する学校もゼロではありません(特に全寮制や集団生活が厳格な校風の場合など)。
志望校の募集要項や説明会情報で、欠席日数や調査書の扱いについて確認しておきましょう。不明な場合は遠慮なく問い合わせて大丈夫です。
学力面でのブランク
不登校期間中に学習が遅れている場合、受験勉強でそのギャップを埋める必要があります。
中学受験の問題は小学校の教科内容を超えた発展的なものも多く含まれます。学校に通っていない間、独学や家庭教師などでどれだけ学習を継続できていたかによっては、受験勉強開始時に苦労するかもしれません。
この点は後述する「準備・対策」の章で詳説しますが、不登校だったぶん学力面でハンデを負う可能性はあります。ただし逆に言えば、時間に余裕があるので集中して勉強に取り組める利点もあります。お子さんの学習状況を客観的に把握し、足りない部分を補う計画を立てましょう。
周囲の目やメンタル面
受験そのものでは不利にならなくても、ご家庭や本人が精神的な不安を抱えがちです。「不登校だったから落ちるかも…」というプレッシャーは本人の自信を削ぎます。
保護者の方は「不登校でも大丈夫」という事例やデータを示し、お子さんを過度に心配しすぎないようにしましょう。実際に不登校から中学受験で成功した例はたくさんあります(後述)ので、「挑戦する価値は十分にある」と前向きに伝えることが大切です。
不登校の子が中学受験を選ぶ理由・メリット
不登校を経験したお子さんが中学受験という道を選ぶ背景には、さまざまな理由やメリットがあります。代表的なものを挙げてみましょう。
環境をリセットして再スタートするため
今の地元小学校で不登校になった原因が、友人関係のトラブルや学校環境のミスマッチにある場合、進学を機に環境を一新したいと考えるのは自然なことです。
中学受験で新しい学校に進めば、人間関係をゼロから築き直せます。
実際、専門の塾講師も「小学生の不登校は先生や友達との相性が原因のことが多いが、受験で環境が変わると通えるようになる子が多い」と指摘しており、中学受験は不登校解決の有効な選択肢の一つだとしています。新天地で心機一転できることは、大きなメリットです。
地元中学に進学しづらい事情があるため
小学校で不登校だった子にとって、地域の公立中学校にそのまま進むのは心理的ハードルが高い場合があります。
特に地方などコミュニティが狭い地域では「不登校だった子」と周囲に知られてしまっていると、余計に学校に行きづらくなるという指摘もあります。いじめを受けて不登校になった子にとっては、加害児童と再び同じ中学に通うことへの恐怖もあるでしょう。このように地元の公立中に進みにくい事情がある場合、中学受験で別の環境に移ることは現実的な解決策になります。
興味・関心や個性に合った学校を選べる
中学受験をすると、各私立中学の多様な教育方針や特色の中から子どもに合った校風の学校を選ぶことができます。
不登校になった要因が「学校の雰囲気になじめなかった」「学習内容に物足りなさを感じた」といった場合、新たに進む学校のカラーを選べるのは大きなメリットです。たとえば理科実験やプログラミング教育に力を入れる学校、部活動や行事が盛んな学校、学習が遅れ気味の生徒へのサポート体制が手厚い学校など様々な選択肢があります。
お子さんの興味関心に合致した私立中なら「楽しそう!◯◯をやってみたい!」と前向きに通えるようになるケースもよくあります。実際、小学校では登校しぶりだった子が「ロボットコンテストが有名な中学」に魅力を感じて受験し、合格後はロボット制作に夢中で毎日学校に通っている、といった例も耳にします。
学校を選べる自由は、不登校だった子にとって学校復帰の原動力になりえるのです。
似たタイプの仲間に出会える
私立中学校では入試を経て似た学力層・志向を持つ生徒が集まります。そのため、小学校よりも人間関係がスムーズになりやすいと言われます。
特に学習意欲が高い子や個性的な子にとっては、公立小より私立中の方が「話の合う友達」が見つかりやすいかもしれません。同じように中学受験を頑張ってきた仲間同士、価値観を共有しやすく、居場所を感じやすくなるでしょう。
実際、とある女子校に進学した不登校経験者の生徒さんは「中学では自分と似た趣味の友達ができ、生き生きと学校生活を送れている」といいます。仲間環境の良さも、中学受験を選ぶメリットの一つです。
大学受験への有利さや将来の展望
全てのご家庭が当てはまるわけではありませんが、「より良い大学に進学させたい」「将来のために良質な教育環境に入れたい」という観点で中学受験を選ぶケースもあります。
不登校だった子の場合、「高校受験よりも中学受験の方が内申点のハンデが少なく進学しやすい」という戦略的判断もありえます。
高校受験では中学3年間の内申点や欠席日数が重く見られるため、不登校経験者にとって選択肢が限られがちです。一方、中学受験なら前述の通り内申不問の学校が多く、「不登校による影響が少ないタイミングで受験できる」という利点があります。
中学から環境を変えて軌道に乗れば、その後の高校・大学への道も開けます。実際、教育現場でも「不登校期間が短い小学生のうちに受験でリセットする方が、その後の復帰がスムーズ」という声が上がっています。将来を見据えて中学受験を再出発のきっかけにすることは、大いに検討する価値があるでしょう。
以上のように、不登校のお子さんが中学受験を選ぶ理由は様々ですが、共通するのは「今の閉塞状況を打開し、より良い環境で再スタートしたい」という想いです。中学受験にはそのチャンスがあり、多くの子ども達がそれを掴んでいます。

学校側の配慮・サポートは?入学後の特別措置を確認しよう
不登校経験のある生徒を受け入れるにあたり、学校側も様々な配慮やサポート体制を整えつつあります。特に私立中学校では、生徒一人ひとりへのケアが手厚い学校が多い傾向があります。
例えば保健室登校(教室に入ることが難しい場合、保健室で自習や別メニューの学習を行うことを許可する)を認めている学校や、オンライン授業の併用を許可して柔軟に対応してくれる学校もあります。
実際、先述の塾講師による調査でも「私立中学はケアが厚く、保健室登校やオンライン授業OKなど柔軟な対応を期待できる学校も多い」と報告されています。また、不登校対応の経験が豊富な学校ではスクールカウンセラーや相談員を充実させ、日々の悩みを気軽に相談できる体制を整えているところもあります。
入学後にもし登校しぶりが再発した場合、どのようなサポートが受けられるかを事前に知っておくことはとても重要です。志望校を選ぶ段階で、以下のポイントをぜひ確認してみてください。
- 代替登校・出席認定の可否: 学校によっては、在籍生徒が塾の自習室で学習した場合や、自宅学習をした場合に「出席」とみなしてくれる制度があるかもしれません。たとえば不登校対応として「週◯日は午後から登校でも出席扱い」「提携するフリースクールに通った場合は出席と認める」等の措置がある学校もあります。このような柔軟性があるかどうかは重要なチェックポイントです。
- 保健室登校や別室・補習対応: 朝のHRだけ顔を出してあとは保健室で過ごしてもよい、放課後に補習を行って学習の遅れをフォローする、といった対応を認めてくれるかも確認しましょう。特に中1のうちは、小学校時代の不登校からいきなりフルタイムで授業についていくのが難しいケースもあります。そうした場合に、一時的な別室登校や個別補習を柔軟に提案してくれる学校だと安心です。
- スクールカウンセラー等の配置: 学校に専属のスクールカウンセラーやメンタルケアのスタッフがどの程度いるかも大切です。週に何日カウンセラーが常駐しているのか、担任以外に相談できる先生がいるのか、といった点を確認しましょう。公立中高一貫校でもスクールカウンセラーは配置されていますが、私立の中にはさらに厚く(常勤で配置、外部専門機関と連携等)している学校もあります。心のケアの受け皿がある学校だと、お子さんも保護者の方も安心して入学後を迎えられるはずです。
以上のようなサポート体制は、学校のパンフレットや公式サイトではあまり前面に出ていない場合もあります。学校説明会や個別相談の機会に、「実は小学校で不登校気味なのですが、入学後のフォロー体制はありますか?」といった形で質問してみると良いでしょう。各校の担当者も率直に情報提供してくれるはずです。
「入学後に再度不登校になってしまった場合、どんな支援が受けられますか?」という問いは、不登校経験者が中学受験校を選ぶ際に最も重要な事項と言っても過言ではありません。遠慮せず確認し、お子さんに合ったサポートが期待できる学校を選んでください。
なお、私立中学の場合「不登校経験者歓迎」などと公に掲げている学校はほとんどありませんが、実際には多くの学校が個別の配慮をして受け入れてくれます。
たとえば過去に不登校だった生徒が在籍している学校では、同じ境遇の後輩を受け入れることにも理解がありますし、そうした生徒に対応した経験を教師が持っています。また、近年は不登校特化型の新設校やコースが中高段階で設けられる例も出始めています(中学受験では少数ですが、高校受験では通信制高校やチャレンジスクールなどが該当)。
中学受験の時点ではそこまで明示的ではないものの、各校とも多様な生徒を受け入れる方向に動いていますので、必要以上に構えすぎず情報収集してみましょう。
実際の合格実績・成功例 ~不登校から花開いた先輩たち~
「本当に不登校から中学受験で成功できるの?」という疑問にお答えするため、実際の成功例やデータをいくつかご紹介します。結論から言えば、不登校を乗り越えて志望校に合格し、新天地で生き生きと学校生活を送っている先輩は全国に大勢います。その一部を知るだけでも、きっと心強い励みになるでしょう。
進学塾での実績データ
首都圏で個別指導塾を運営する塾長の山田佳央氏(不登校の子の受験指導を多数経験)によれば、「小学生の不登校生徒の約90%が中学受験を機に状況が改善し、学校復帰している」といいます。
実際、2022年度には同氏の塾で不登校状態から受験に挑み合格した10名以上のお子さんのほとんどが、合格した中学校へ元気に通えているとのことです。小学生のうちに受験で環境を変えた子は高い確率で学校生活に戻れている、という心強いデータです。
ある女子生徒のケース
東洋経済オンラインの取材記事では、小5の11月からいじめによる不登校を経験し、「わけあり中学受験」に挑んだ都内在住の女の子のエピソードが紹介されています。
彼女は小学校で陰湿ないじめに遭い登校不能になりましたが、「人間関係を変えたい、新しい環境でやり直したい」という強い思いから中学受験を決意。
猛勉強の末見事志望校に合格し、現在は芸術系科目が充実した女子校に通って生き生きと暮らしているそうです。苦い経験をバネに努力し、自分に合った最適な環境を選び取った成功例と言えるでしょう。
「不登校=不合格」ではない現実
文部科学省のいじめ防止対策協議会でも、「多くの中学受験生の中に小学校時代に不登校になった子が交じっている」ことが異例ながら報告されています。
これは裏を返せば、不登校だった子も実際に多数合格して進学しているという事実です。
例えば首都圏では、中学受験を経て私立中に進学する生徒全体の7%前後(全国平均)の中に、不登校経験者も一定数含まれていると推察できます。中には難関校に合格したケースもあり、不登校だからといって学力が劣っているわけではないことを示しています。
「不登校だけど◯◯中学に合格した」という体験談は、ネット上のブログやQ&Aサイトでも多数見受けられます。そうした先輩たちが新しい学校で充実した日々を過ごしていることは、大いに希望を与えてくれます。
入学を機に学校復帰できた例が多数
不登校支援に取り組む教育者によれば、「小学生は不登校期間が短く学力の遅れを取り戻しやすいので、中学受験を契機に復帰しやすい」といいます。実際、「5年生の2月から準備して難関私立中に合格」「6年生の秋からの追い込みで合格」といった短期決戦で成果を出した子もいるとのこと。
入学後も、そうした子たちは周囲のサポートを得ながら元気に通学を続けています。入学をきっかけに不登校が解決するケースは非常に多いのです。このことは、「今は不登校だけど、受験して新しい学校に入ればきっと大丈夫」と前向きに考える根拠になるでしょう。
以上のように、不登校から中学受験を経て成功した事例は数多く存在します。不登校だった過去は決してハンデではなく、むしろ「あの経験があったからこそ今の自分がある」と糧にしている子もいます。
保護者の方にとっても、お子さんの努力と環境次第で状況は好転しうるという事実は大きな励ましになるのではないでしょうか。
著名人の事例「不登校→中学受験→リスタート」のリアル
著名人のなかにも、小学校でつまずいても、中学受験をきっかけに環境を変え、前向きに歩き出した例は少なくありません。
ここでは山崎怜奈さん(タレント/元乃木坂46)とコレコレさん(YouTuber)の公表情報から、「小学校で不登校でも中学受験でリスタートできる」具体像を整理します。
ケース1:山崎怜奈さん―「地元に馴染めない」違和感からの決断
小学校時代、クラスや校則の雰囲気に強い違和感を抱え、「完全な不登校ではないが、行ったり行かなかったり」の時期があったと語っています。
小6の夏に地元中ではなく中学受験で環境を変える決意をし、都立一貫校は不合格だったものの、私立・郁文館中学校に進学。そこから学び直し、大学受験でも成果を重ねています。
ポイント:
「いじめや校風のミスマッチで消耗しているなら、中学で環境を変える選択は有効」だと本人の体験が示しています。なお、ご本人は「完全な不登校ではなかった」とも明言しており、グラデーションのある状態からでも受験をテコに軌道修正できることがわかります。引用元・参考情報:Hanako Web、HugKum、CHANTO WEB、朝日新聞
ケース2:コレコレさん―小6で不登校→私立中へ進学
小学校でいじめを受け、6年から不登校に。そこから受験で地元の私立中学に進学し、のちに配信者として大成します。
経緯は本人の著書(宝島社)内容を引用する形でメディアでも紹介されています。学校名までの特定は公的資料では明言されていないものの、「不登校→受験→私立中へ」という進路転換がはっきり示されています。
ポイント:
不登校の渦中でも、入試という“当日の実力”で評価されるルートを選ぶことで再スタートが可能になります。中学受験は内申や出席の影響が小さい学校も多く、学力到達が合否の主因になりやすいからです(学校により扱いは異なります)。
2人の共通項から学べること
- 「環境を変える勇気」が転機になります。合うコミュニティに移るだけで、通学や学習のモチベーションが回復することがあります。
- 評価軸の切り替えが効きます。中学受験は当日の試験(または適性検査)比重が高く、過去ではなく“今の力”で見てもらえる機会になりえます。
- 保護者の情報収集と対話が鍵です。学校説明会や個別相談で入学後のサポート(別室登校・カウンセラー配置・出席認定の柔軟性など)を確認し、お子さん本人の納得感を大切に進めると、入学後の定着率が上がります。
まとめ
小学校で不登校でも、中学受験は環境を変えてリスタートする現実的な選択肢になります。
山崎怜奈さんのように「馴染めなさ」を受験で乗り越えた例も、コレコレさんのように「いじめ→不登校」から軌道修正した例も、いずれも“行き先を選ぶ”ことで人生の流れを変えたという点で共通しています。まずはお子さんの心身の安定を優先しつつ、「合う学校」を丁寧に探していきましょう。
不登校からのリスタートを後押しする「オンライン個別指導」2選
小学校で不登校を経験しても、学びの再起動ができれば中学受験は十分に目指せます。ここでは、在宅で学習ペースを立て直しやすい不登校専門オンライン個別指導を2つご紹介します。
どちらも“今の状態”から逆算して進める仕組みがあり、保護者との連携も前提にしたサービスです。
※成果や効果はお子さんの状況・取り組み時間により個人差があります。出席扱いは学校長の裁量に基づき判断されます。
① 不登校専門オンライン塾【巣立塾】— 苦手が出やすい英数の“基礎固め×習慣化”
- 不登校に特化した設計。復学支援「スダチ」の知見をベースに、在宅で学び直しができるオンライン個別指導です。復学支援サービスとして1,500名以上の再登校支援実績があることも安心材料になります。
- 英語・数学の基礎固め+授業後レポート。“つまずきやすい英数”を基礎からやり直し、毎回の授業後に報告書で保護者へ学習状況を共有。小1〜高3まで幅広く対応しています(申込フォームの学年選択より確認可)。
- 在宅で始めやすい。完全オンラインのマンツーマン指導で、通塾ストレスを避けつつ“勉強のリズム”を再構築できます。
▶ 公式サイトを見る:不登校専門のオンライン塾【巣立塾】
② きっかけを作る!【ティントル】— 学習×メンタル×家庭の三位一体サポート
- “勉強を教えるだけ”にしない体制。指導のほかに保護者向けの並走サポートを設け、担当スタッフが面談や計画調整を担います。スタッフには「教育カウンセラー1級 不登校心理相談士」資格を持つメンバーが在籍。根本課題にも並走します。
- 完全マンツーマン+相性マッチング。お子さんの特性や興味に合わせ、相性の合うチューターをマッチング。学び直しと自己効力感の両方を狙います。
- 「出席扱い」申請をサポート。オプションのホームスクーリングコース(月8,800円)では、学習記録の作成・提出など出席扱いの申請をサポート(判断は学校長)。公式サイトでも「申請が可能」と明記されています。
▶ 公式サイトを見る:出席扱いサポート制度あり【ティントル】
どちらが合う?選び方の目安
- まずは状態起点で:
「英数の穴を短期で埋めたい」「学習報告をこまめに受けたい」→不登校専門のオンライン塾【巣立塾】
「学習とメンタル支援をワンパッケージで」「出席扱いを相談したい」→出席扱いサポート制度あり【ティントル】 - 出席扱いの可否は学校と相談:
文科省のガイドラインに沿っても最終判断は学校長です。申請や書類作成をサービス側が支援してくれるかを確認しながら、在籍校と連携して進めましょう。
親子の“再スタート”を現実に
山崎怜奈さんやコレコレさんのように、環境を変える決断が転機になるケースは少なくありません。オンライン個別指導を活用して「できた」を増やすことは、前を向くきっかけになります。無理のない一歩から始めていきましょう。
中学受験に向けた準備と保護者のサポート
最後に、不登校のお子さんが中学受験に挑むにあたって、どのような準備や心構えが必要かをまとめます。これは保護者の方へのアドバイスにもなります。
1. お子さんの心身のケアを最優先に
中学受験の勉強は決して楽なものではなく、学校に通っている他の受験生と比べると困難な道になる可能性があります。
不登校のお子さんの中には、いじめや挫折で心に深い傷を負っているケースもあります。まず大前提として、お子さんの精神的な健康を最優先に考えてください。
受験勉強どころではなくメンタルケアを優先すべき状況であれば、無理に勉強を詰め込まない方が良いです。例えばカウンセリングに通ったり、親子でゆっくり休養したりする時間も必要でしょう。十分な心のケアがなければ、受験に臨んでも途中で折れてしまうかもしれません。
また、お子さんが「本当にその中学に行きたいと思っているか」も大切です。
親御さんの焦りから半ば強引に受験させられる形になると、勉強へのモチベーションが続かず、合格しても入学後に再び不登校になってしまうケースもあります。お子さん自身の意思を尊重し、「中学からは変わりたい」「◯◯中に行きたい」という気持ちが湧いているかを確認しましょう。
もし今は乗り気でなくとも、学校見学に行ったり実際に合格者の体験談を読んだりする中で意欲が出てくる場合もあります。焦らず、お子さんのペースに寄り添ってあげてください。
2. 学習計画と勉強法の工夫
不登校の期間が長かった場合、勉強面では小学校内容の抜け落ちがあるかもしれません。
特に中学受験の勉強は特殊で、小学校の授業をしっかり受けていた子でも塾で専門のテクニックを学ばないと太刀打ちできない世界です。したがって、受験を決めたら早めに学習計画を立て、効率的な勉強法を検討しましょう。
塾や家庭教師の活用
可能であれば中学受験専門の進学塾や個別指導塾、家庭教師などプロの力を借りることをお勧めします。
塾に通えるのであればベストですが、集団塾に馴染めない場合は個別指導やオンライン指導という選択肢もあります。最近はオンライン家庭教師や映像教材も充実していますので、お子さんに合った学習環境を選んでください。
不登校のお子さんの場合、自宅で一人で勉強するのは意志の維持が難しいこともあります。漫画やゲームがすぐ手の届く所にあるとつい誘惑に負けてしまい、「時間はあるのにあまり勉強できなかった」という事態にもなりがちです。そうした意味でも、塾や家庭教師による半強制力・ペースメーカーは有効です。
基礎の総おさらい
勉強を始める際は、まず小学範囲の基礎学習を漏れなく固めましょう。特に不登校期間中に習っていない単元がある場合、そこは飛ばさず戻って学び直す必要があります。
例えば算数の計算や文章題の基礎、国語の漢字や読解の基礎など、小学校内容で穴があると中学受験問題にも支障が出ます。中高生になってから不登校だと九九の計算から教え直すケースもありますが、小学生の場合は範囲がまだ少ない分、遡って学び直す量も比較的少なくて済みます。
保護者の方も一緒に計画を立て、どこから手を付けるべきか整理してあげると良いでしょう。
無理のない目標設定
学校選びの際には、お子さんの現在の学力やペースを踏まえて無理のない志望校レベルを設定しましょう。
親心としてつい「せっかく受験するなら少しでも偏差値の高い学校へ…」と思いがちですが、レベルが高すぎる志望校を選んでしまうとお子さんに過度な負担とストレスがかかります。不登校からの受験では特に、「確実に狙える範囲の学校を選ぶ」ことが大切です。
中学受験の偏差値は全小学生の上位約10%の中での偏差値なので、偏差値50でも一般的な小学生から見るとかなり高い学力水準です。そのことを念頭に置き、「今のうちの子ならこの辺りが妥当かな」というラインを見極めましょう。第一志望校だけでなく第二志望・第三志望も含め、複数校を受けるプランを立てておくと安心です。
3. 経済的・時間的コストへの理解
中学受験はご家庭にとって経済的・時間的負担も大きいイベントです。不登校からの挑戦であってもそれは変わりません。
塾の授業料や教材費、家庭教師の謝礼、受験校の受験料、合格後の入学金・授業料など、金銭的コストは相当かかります。私立中学へ進む場合、6年間で数百万円以上の学費・諸経費が必要になることもあります。まずはご家庭の予算や方針を整理し、「ここまでなら出せる」というラインを明確にしておきましょう。経済的な理由で途中リタイア…ということにならないよう、事前に現実的な計画を立ててください。
また、親御さんの時間と労力も覚悟が要ります。
送迎やお弁当作り、模試の付き添い、メンタル面のフォローなど、中学受験は親の協力なくして成り立たないとも言われます。「中学受験は親の受験」といった言葉もあるほどで、子どもを支えるサポーターである親の役割は非常に重要です。お子さんが勉強に集中できるよう、生活リズムの管理や雑事のフォローなど、家庭内でのサポート体制を整えましょう。
保護者の方自身の心と体にも余裕が必要ですので、無理をしすぎず周囲(夫婦で協力したり、場合によっては祖父母の助けを借りたり)に頼れるところは頼ってください。
4. 不合格への備えとその後の選択肢
残念ながら受験がうまくいかなかった場合のシミュレーションも、予め考えておく必要があります。
第一志望校に合格できる確率は一般に30%程度とも言われ、複数校受けても全滅してしまう生徒も珍しくありません。不登校からの受験となると、合格を勝ち取った後の学校生活こそが本番ですから、万一不合格だった際にお子さんが過度に落胆しないようケアすることが大切です。
不合格だった場合の進路としては、地元の公立中学校に進学するのが基本となります。中学受験を経て公立中に進む子も世の中には一定数いますし、それまでの受験勉強で学力が上がっていれば、公立中でスムーズに適応できる可能性も高まります。
また、地域や状況によってはフリースクールや適応指導教室に通いながら、公立中に在籍するという選択肢もあります。高校受験以降で再チャレンジする道も残されていますので、仮に中学受験で思うような結果が出なくても決して将来が閉ざされるわけではありません。保護者の方は、もしもの時には「公立中でリベンジしよう」「高校受験や大学受験でまたチャンスがあるよ」と先を見据えた声掛けをしてあげてください。
不合格直後はお子さんもナーバスになっていますから、無理に慰めたり説得したりせず、しばらくは静かに見守ることも時には必要です。その上で、落ち着いてきたら次の一手を一緒に考えてあげましょう。「公立中でも支援級や別室登校でやってみよう」「◯◯高校(通信制や定時制など)を目指してみようか」など、決して道は一つではないことを伝えることが大事です。
5. 周囲のサポートと情報収集
不登校からの中学受験は、決して一人(一家庭)で抱え込む必要はありません。同じ境遇の仲間や先輩保護者、プロの力を上手に借りましょう。
インターネット上には不登校児の受験体験談を綴ったブログや、Q&Aサイトでの相談投稿なども多数あります。それらを読むだけでも有益なヒントや励ましが得られます。また、学校の先生やカウンセラーにもぜひ相談してください。小学校の担任の中には「中学から再スタートしたい」という生徒の気持ちを理解し、陰ながら応援してくれる方もいます。
教育委員会の不登校支援担当部署に問い合わせれば、進路指導について助言をもらえることもあります。塾に入れば、塾の先生が受験校選びからメンタルケアまで親身に相談に乗ってくれるでしょう。不登校の子の受験指導経験が豊富な塾や家庭教師も増えてきています。
「周囲にもっと頼っていい」ということを、保護者の方自身が自覚することも大切です。
まとめ
小学校で不登校を経験したお子さんでも、中学受験によって新たな環境で再出発を切ることは十分可能です。受験制度の上でも不利なく挑戦できる場合が多く、実際に多くの先輩たちが成功を収めています。不登校だった過去は決してお子さんの可能性を狭めるものではありません。
大切なのは、「お子さんに合った学校選び」「入学後のサポート体制の確認」「無理のない受験計画」「心のケアと学習支援の両立」です。不登校の経験を乗り越えて合格を勝ち取った暁には、きっとお子さんは一回り成長し、自信を持って中学校生活をスタートできることでしょう。
その日を信じて、親子二人三脚で準備を進めてみてください。陰ながら応援しています。




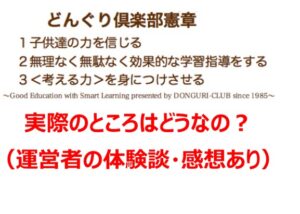
コメント