中学受験に取り組むご家庭の間で、最近「NN勉強法」という勉強法が注目を集めています。実は人気子役の芦田愛菜さんもこのNN勉強法を実践し、見事に慶應義塾中等部に合格したことで話題になりました。
一体このNN勉強法とはどのような方法なのでしょうか?
本記事では、NN勉強法の定義や由来、基本的な考え方、中学受験で注目される理由、他の勉強法との違い、具体的な取り入れ方、成功例や体験談、さらには注意点や向き不向き、保護者ができるサポートまで、網羅的にわかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、お子さんの中学受験勉強にNN勉強法のエッセンスを取り入れるヒントにしてみてください。
NN勉強法とは何か(定義と由来)
NN勉強法とは、「何が何でも志望校に合格する」ことを目指した勉強法です。「何が何でも」の頭文字をとって「NN」と名付けられました。その名のとおり、「絶対に志望校に受かってみせる」という強い意志を持ち、志望校の入試傾向に徹底的に合わせた勉強をひたすら行う方法です。
通常、中学受験では複数の志望校を受験するため、それぞれの過去問に目を通すなどバランスよく対策します。しかしNN勉強法では志望校を1校に絞り、その学校だけに照準を定めて対策を行う点が最大の特徴です。
この勉強法はもともと、大手塾である早稲田アカデミーが開発した「NN志望校別コース」で実践されていた指導法から生まれました。早稲田アカデミーでは、開成や麻布、桜蔭、慶應義塾中等部など難関中学校ごとに専門クラス(NNコース)を設け、各校の入試問題を徹底分析して作成したオリジナル教材で指導しています。例えば「開成クラス」ならクラスの全員が開成中学志望であり、担当講師は開成中の入試だけを研究して指導します。
このように志望校ごとに特化した指導を行うことで、「何が何でも合格したい」という受験生の熱意に応えるカリキュラムとなっているのです。
なお、「NN」という名称については前述の通り「何が何でも」の略ですが、この強い覚悟を端的に表現した名前が中学受験生や保護者の心に響き、現在では特定の塾に限らず広く知られる勉強法の呼称として定着しつつあります。
NN勉強法の基本的な考え方と仕組み
NN勉強法の基本理念はシンプルで、「第一志望校の合格可能性を最大限に高めること」です。そのために、志望校の入試傾向を徹底的に調べ尽くし、対策を集中するという仕組みになっています。
具体的には、志望校の過去問をくまなく分析して頻出分野や出題パターンを把握し、それに沿った演習と対策を繰り返します。ポイントは「この学校で問われる力」に絞って勉強することです。
例えば、ある学校の入試で作文が重視されるなら徹底的に記述練習をする、理科の実験考察問題が多ければ類題演習を積む、といった具合にピンポイントで必要な力を鍛え上げるのです。
また、NN勉強法では勉強時間と集中力も重要なキーワードです。
過去問研究に基づいて方針が定まったら、あとは「何が何でも合格する」という信念のもとでひたすら勉強を継続します。時には長時間の勉強も辞さない覚悟で取り組むため、必然的に勉強時間が増え、集中力や学習体力も養われます。実際、NN勉強法の元祖である早稲田アカデミーのNNコースでは毎回膨大な宿題が課され、子どもたちは週末や休みの日も自宅学習に充てざるを得ないほどだといいます。
それだけ聞くと「それなら家でも大量の勉強をさせればいいのでは?」と思うかもしれませんが、小学生に「とにかく勉強させる」ことは実は極めて困難です。ゲームや遊びたい誘惑に負けず勉強漬けにするには、本人の強いモチベーションと周囲の仕掛けが必要です。
NN勉強法ではその点、同じ志望校合格を目指すライバルと切磋琢磨できる環境や、選抜されたエリート意識から来る自負心、「絶対合格するぞ」という強い気持ちを引き出す工夫があり、結果として子ども達に猛烈な勉強を継続させる原動力となっています。
まとめると、NN勉強法の仕組みは
- (1)第一志望校を明確に一校に定める
- (2)その学校の入試問題を徹底分析して対策方針を決める
- (3)長時間の集中的な演習で必要な実力を一気に高める
――という流れになります。その過程では志望校以外のことは思い切って捨てる大胆さも求められます。まさに全リソースを一校合格に傾ける「一点突破型」の勉強法と言えるでしょう。
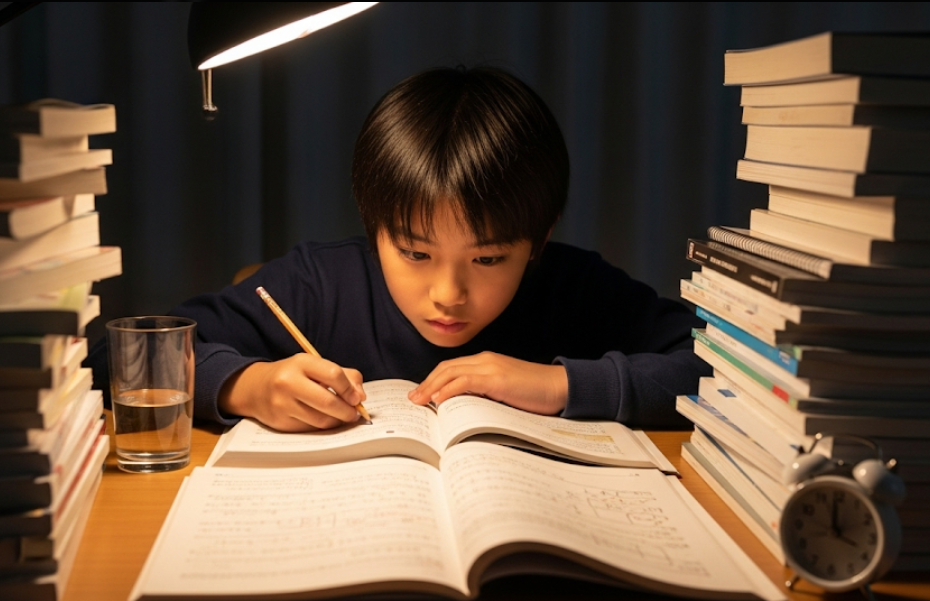
NN勉強法が中学受験で注目される理由
では、なぜこのNN勉強法が近年中学受験でこれほど注目されるのでしょうか?大きく分けて効果の高さと実績・話題性の2点が挙げられます。
まず効果の高さですが、NN勉強法は前述のように志望校対策に時間と労力を集中的につぎ込むため、短期間でも合格率を効率よく高められる点が魅力です。たとえ受験勉強のスタートが遅れてしまった場合でも、志望校を絞って重点的に勉強すれば挽回できる可能性があります。実際、「夏からNNの特訓コースに入って一気に成績が伸び、志望校合格ラインに届いた」という受験生も珍しくありません。
また、周りと同じペースの集団塾授業に比べて差別化が図れるのも強みです。
普通の塾で皆と同じ内容を同じように勉強しているだけでは周囲に埋もれてしまいますが、NN勉強法なら志望校に特化した対策のおかげでグッと合格に近づけるのです。集中して長時間勉強する経験を積むことで、本番での集中力や粘り強さも養われるという副次的なメリットもあります。
このように「なんとしても合格する」という強い意志と合理的戦略が組み合わさったNN勉強法は、合理性を重んじるご家庭から高く評価されています。
次に実績・話題性の面では、やはり著名な成功例が大きいでしょう。
冒頭でも触れたように、芦田愛菜さんは多忙な芸能活動の合間を縫ってNN勉強法を実践し、慶應義塾中等部をはじめ複数の難関中学に合格しました。彼女は受験直前の5ヶ月間に1日12時間もの勉強時間を確保したと言われており、その徹底ぶりが注目を集めました。
幼少期からご両親のきめ細かなサポート(学校内容の復習を家庭で黒板を使って行うなど)を受けて育ち、移動中や楽屋、入浴中に至るまですき間時間をすべて勉強に充てていたという逸話もあります。このようなエピソードがメディアで紹介されたことで、「NN勉強法=短期間で最大の成果を生み出す画期的な方法」というイメージが広まり、多くの保護者の関心を引いたのです。
加えて、早稲田アカデミーのNNコースからは毎年のように難関校合格者が多数輩出されています。公式発表される合格体験記などを見ても、「6年生秋からNN◯◯コースに入り志望校対策に専念した結果、最後の模試で合格圏に届き合格できた」「NNで出された大量の課題をやり抜いたことが自信につながった」といった声が多く、成功体験が蓄積されています。
ある受験生は「NNの授業や宿題を通じて、入試問題を様々な視点から見ることを楽しめるようになり、自信を持って本番に挑めた」と述べており、徹底した対策がむしろ試験への余裕と楽しさにつながったという証言もあります。また別の受験生は「NNで出会った仲間と励まし合えたおかげで最後まで弱音を吐かず頑張れた。当日も同じ志望校の友達の存在に励まされた」と振り返り、切磋琢磨できる環境が精神面の支えになったと語っています。
こうした具体的な成功例が口コミやインターネットを通じて広まり、「うちの子もNN勉強法を取り入れれば志望校合格に近づけるかも」と期待するご家庭が増えているのです。
以上のように、NN勉強法が注目されるのは「合理的で効率が良い」「実際に成果が出ている」という確かな理由があるからだと言えるでしょう。

他の勉強法との違いと比較(過去問重視・スパイラル学習など)
中学受験にはNN勉強法以外にも様々な勉強法・指導方針がありますが、NN勉強法はそれらとどのように異なるのでしょうか。ここでは代表的な例として「過去問重視の勉強法」と「スパイラル学習(螺旋型学習)」と比較しながら特徴を見てみます。
過去問重視の勉強法との比較
過去問重視とは、その名の通り志望校の過去問演習を中心に据える勉強法です。
中学受験では一般的に秋以降に志望校の過去問演習を行い、本番形式や出題傾向に慣れるのが定石です。第一志望校については直近10年分程度、併願校も5年分程度を解いて傾向をつかむのが標準的な進め方でしょう。NN勉強法も過去問研究を重視する点では共通していますが、その過去問の使い方と集中度合いが異なります。
通常の過去問演習では第一志望だけでなく複数校の問題に取り組みますし、過去問演習の開始時期もカリキュラム修了後の秋(9月以降)が推奨されています。一方NN勉強法では、もっと早い段階から第一志望校の過去問に的を絞り込んで分析し、対策教材に反映させることが多いです。早稲田アカデミーのNNコースでは夏期講習以降、本格的に志望校別の特訓体制に入ります。これは言わば「過去問重視」を徹底的に推し進め、過去問の徹底研究+演習を軸に据えたカリキュラムに他なりません。
このようにNN勉強法は過去問重視型勉強法の究極形とも言えます。違いがあるとすれば、NN勉強法の方が対象を1校に限定することで過去問演習の効果を最大化している点でしょう。他校の問題に手を広げないぶん、志望校の問題を繰り返し解き込み、類似パターンの問題演習や対策にも時間を充てられます。
その反面、「他校の問題に触れる機会が減る=視野が狭くなる」リスクもありますが、それを承知の上でメリハリをつけているのがNN勉強法と言えます。要は「広く浅く」ではなく「狭く深く」がNN流なのです。
スパイラル学習(螺旋型学習)との比較
スパイラル学習とは、カリキュラム上同じ単元を何度も繰り返し(螺旋状に)学習することで理解を定着させる勉強法です。
多くの進学塾で採用されており、学年が上がるごとに同じ分野をより高度な内容で再度学ぶことで力を伸ばす方式です。例えば小4で習ったことを小5で発展させ、小6で入試レベルまで高める…というように段階的にレベルアップしていきます。
スパイラル方式の利点は、多少理解が不十分な単元があっても次の機会で補強できる点や、時間をおいて繰り返すことで記憶が定着しやすい点です。一方、NN勉強法は短期間で志望校合格力を仕上げる一点突破型ですから、カリキュラム全体を螺旋的に回して基礎力を底上げするという発想とはアプローチが異なります。
極端に言えば、「この志望校合格に必要なこと以外は一旦置いておく」という割り切りをするのがNNであり、「全科目全単元まんべんなく発展させながら何度も復習する」のがスパイラルです。
どちらが優れているというより、目的と時期が違うと言えるでしょう。
中学受験全体の長期戦略としてはスパイラル方式で基礎学力を盤石にし、最終段階でNN的に志望校対策へ一点集中する——これはある意味理想的な組み合わせです。実際、多くの塾では小4〜小5前半でスパイラル型の復習を重ねて学力の土台を作り、6年生後半には過去問演習や学校別特訓(NNコース等)で志望校対策に注力します。したがって、スパイラル学習とNN勉強法は対立するものではなく、受験勉強の前半と後半で役割が異なるものと捉えるのがよいでしょう。お子さんによっては、まずは広く基礎固めをするスパイラル方式で力をつけ、自信の第一志望が固まった段階でNN的な勉強法にシフトするというプランも効果的です。
以上のように、NN勉強法は「過去問活用の徹底度」「志望校への特化度」という点で他の勉強法と一線を画しています。過去問重視派の方にとってNN勉強法は参考になる部分が多いですが、ただ闇雲に過去問を解くだけでなく徹底分析して対策を練る戦略性こそNN流の真骨頂です。またスパイラル学習のようなオーソドックスな手法とも組み合わせ可能であり、状況に応じて両者の長所を取り入れる柔軟さも大切です。

NN勉強法の実際の取り入れ方(自宅学習・塾併用)
NN勉強法に興味はあるものの、「実際にどう取り入れればいいの?」と悩む保護者の方も多いでしょう。ここでは、塾での活用方法と自宅学習で取り入れる方法の両面から具体的なアドバイスを紹介します。
塾のコースや特訓を活用する方法
お子さんが既に進学塾に通っている場合は、まずその塾に志望校別特訓コースや学校別対策講座があるか確認してみましょう。早稲田アカデミーのように「NNコース」と銘打っていなくても、塾によっては6年生の後期に志望校対策の特別講座を用意しているところもあります。
例えば、SAPIXでは秋から難関校別の特訓講座(SS特訓)が開講されますし、四谷大塚でも志望校別の模試や対策講座があります。そうした志望校対策に特化したプログラムに積極的に参加することで、NN勉強法のエッセンスを取り入れることができます。
もしお子さんの通塾先に該当コースが無い場合でも、他塾の特別講座を併用受講する選択肢もあります。実際、メインの塾とは別に早稲田アカデミーのNN志望校別オープン模試を受験し、志望校対策の情報を収集したりすることも多いです。
このように他塾の模試や特訓を併用することで、志望校の入試傾向や必要な学習項目を把握することも可能です。塾同士のカリキュラム調整や時間確保が大変な場合もありますが、志望校対策が充実している環境を上手に取り入れることが合格への近道となります。
塾の特訓を利用する最大の利点は、効率よく傾向分析された教材と指導が手に入ることです。個人で一から志望校の出題傾向を研究するのは時間と労力がかかりますが、塾なら蓄積されたデータやノウハウがあります。実際、早稲田アカデミーなど大手塾では何年分もの入試問題を徹底的に分析し尽くし、対策法が体系化されています。その成果であるテキストや授業を活用できるのは大きなアドバンテージです。
「NN勉強法=必ずしもNNコースに入らなければできない」というわけではありませんが、やはりプロの分析力と指導力を借りられるなら大いに活用した方が効率的でしょう。
自宅でNN勉強法を実践する方法
一方で、「塾に頼らず家庭でNN勉強法に取り組みたい」「地方在住でNNコースのようなものが近くにない」というご家庭もあるでしょう。個人でもNN勉強法は十分実践可能です。以下に、家庭でNN勉強法を取り入れる手順の一例を示します。
①第一志望校を明確に決める
まずはお子さんと相談の上、「ここだけは何が何でも合格したい!」と思える志望校を1校に絞り込みます。他にも受験校はあるでしょうが、NN勉強法を適用する「最優先校」を決めるイメージです。志望校選びはお子さんの学力や適性、夢などを踏まえて慎重に行いましょう。
覚悟を持って臨むためにも、本人が心から行きたい学校であることが大切です。
②志望校の入試情報・過去問を徹底研究する
志望校が決まったら、早い段階から過去問題集を入手し、入試傾向の研究を始めます。過去問は書店で来年度用が発売されたらすぐ購入し、ご家庭で分析に取りかかりましょう。お子さん自身に解かせるのはカリキュラムが一通り終わってからで構いませんが、親御さんはできるだけ早く目を通しておくことをおすすめします。
問題の難易度や出題形式、頻出分野、合格最低点の目安などをチェックし、「合格に必要な学力との差」を把握しましょう。場合によっては塾の先生に相談し、傾向分析のアドバイスをもらうのも良いでしょう。
③対策計画を立てる
過去問研究を踏まえて、「何を重点的に勉強すべきか」の計画を立てます。
例えば「算数の図形問題で高得点を狙う必要がある」「理科は実験考察が頻出なので演習量を増やす」など、志望校合格に直結する分野にフォーカスした学習メニューを洗い出します。通常の塾の宿題や学校の勉強もあるので大変ですが、NN勉強法を取り入れるなら優先順位を明確につけることが肝心です。
塾の課題もすべて完璧に…と欲張ると時間がいくらあっても足りません。場合によっては「塾の通常授業の内容を取捨選択する」「家庭学習では志望校対策を最優先する」といった思い切ったメリハリも必要です。お子さんの弱点科目や課題も考慮し、どこにどれだけ時間を配分するかスケジュールを組みましょう。
④徹底的に実行・演習する
計画が決まったら、あとはひたすら実行あるのみです。
【何が何でも合格】というスローガンをお子さんと共有し、「〇〇中に絶対入るぞ!」と日々声に出してみても良いでしょう。具体的には、志望校の過去問を年度別に解いてみて弱点を洗い出し、出題パターン別に類題集や参考書で集中的にトレーニングします。繰り返しになりますが、この段階では志望校に関係の薄い勉強は思い切って後回しにします。
例えば他の併願校の問題演習は後述のとおり時期を遅らせる、塾のテキストでも志望校対策に不要な単元の深追いはやめる、などです。
【何を捨て何に集中するか】親子で合意しておくと、迷いなく勉強に打ち込めます。また、お子さんが集中して長時間勉強できる環境作りも大切です。静かな学習スペースの確保、テレビやゲーム機の撤去、スマホ利用時間の制限など、必要に応じて環境を整えましょう。場合によっては図書館や自習室を積極的に利用したり、同じ志望校を目指す仲間と切磋琢磨する場を作ったりするのも効果的です。
⑤定期的に振り返り調整する
NN勉強法で突き進んでいると、どうしても志望校以外が見えにくくなります。定期的に模試を受けて客観的な立ち位置を確認しましょう。合不合判定テストなど大手模試での志望校判定をチェックし、合格可能性があまりに低いようなら勉強内容の修正や併願校戦略の見直しも必要です。
「第一志望一本に絞る」とはいえ、万一に備えて併願校の過去問にも秋以降には取り組む時間を確保してください。一般的には9月中旬の模試(第3回合不合)終了後くらいから、週1回ペースで他校の過去問演習を開始すると良いでしょう。NN勉強法実践中でも、リスク管理として最低限の併願校対策は忘れないようにしてください。
家庭でNN勉強法に取り組む場合、保護者の役割が非常に大きくなります。
具体的な保護者のサポート術については後述しますが、親御さんが半分「家庭教師」や「マネージャー」のような気持ちで伴走するくらいのイメージでいると良いでしょう。【塾任せにしない主体的な受験勉強】が、NN勉強法を成功させるカギとなります。

NN勉強法の成功例・体験談紹介
NN勉強法を取り入れた受験生の成功例や体験談をいくつかご紹介します。実際の声を知ることで、この勉強法への理解がより深まるでしょう。
芦田愛菜さんの成功例
前述の通り、芸能活動と学業を両立させて難関中学に合格した芦田愛菜さんはNN勉強法の代表的成功例です。
彼女は小学6年生の夏以降約5ヶ月間、毎日10〜12時間もの勉強を続けたとされています。早稲田アカデミーのNNコースに通い、志望校である慶應義塾中等部の対策を徹底的に行いました。過去問研究はもちろん、苦手分野はご両親とともに黒板で復習するなどあらゆる手を尽くしたそうです。
その結果、慶應中等部だけでなく栄光学園や立教女学院など複数校に合格する快挙を成し遂げています。彼女の体験はメディアでも大きく取り上げられ、「短期間で成果を出すNN勉強法」の存在を広く知らしめました。
NNコース生の合格体験談
早稲田アカデミー公式サイトの合格者体験記には、NN志望校別コースで学んだ生徒や保護者の声が掲載されています。その中からいくつか印象的なエピソードを紹介します。
ある男子生徒は小6の夏にNN麻布クラスに入り、本番まで走り抜けました。当初、四谷大塚の合不合判定テストでは一度も合格可能性50%以上を取れなかったそうですが、NNで麻布中の思考力重視の問題に慣れた結果、最後の志望校別模試では合格ラインに達し、見事本番でも合格できたとのことです。「NNの授業や宿題で学んだ解き方を実践し、入試問題を様々な視点から楽しんで解けたこと、自信を持って挑戦者として挑めたこと」が合格につながったと振り返っており、辛い特訓も前向きな気持ちで乗り越えられた様子が伝わってきます。
別の生徒は、「NNで出会った同じ志望校志望の友達が最大のライバルであり仲間になった」と語っています。入塾当初は友達ができず不安もあったようですが、切磋琢磨するうちに強い絆が生まれたそうです。「入試本番でもNNの友達の顔を見て落ち着いて臨めた」といい、緊張する試験会場で心強い支えになったようです。また彼は国語が苦手科目だったものの、NNの先生が徹底的に記述答案を添削指導してくれたおかげで得点力が上がり、自信を持って本番に臨めたと言います。「合格できたのはNNの先生方と仲間のおかげ」と感謝の言葉を述べており、NN勉強法の環境が持つ力を物語っています。
ある保護者の方の声では、「息子はNNの先生に徹底的にサポートしていただき、何とかくらいついていった。後半の志望校別模試では合格ラインを超えるまで成長し、最後に合格を勝ち取った。ここまで頑張り抜いた息子に感動するとともに、信じて導いてくださった先生方に大変感謝している」というエピソードも紹介されています。ご家庭と塾が二人三脚でお子さんを支えた成功例と言えるでしょう。
これらの体験談から学べるのは、NN勉強法は単なる勉強テクニックではなく「環境」と「精神面」の効果が大きいということです。
徹底した志望校対策によって学力が伸びるのはもちろんですが、それ以上に「同じ目標に向かう仲間の存在」「厳しい特訓をやり遂げた自信」「絶対合格するという強い気持ち」が合格を引き寄せている様子がうかがえます。NN勉強法を家庭で再現する際も、ぜひこの点を意識して、お子さんのモチベーションやメンタル面のサポートに力を入れてみてください。
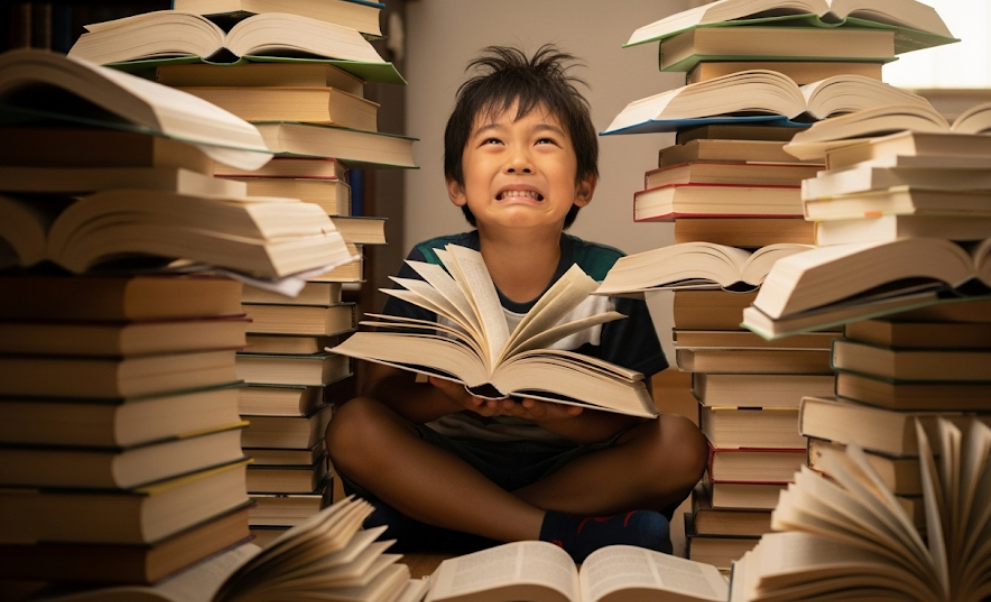
NN勉強法の注意点やデメリット
ここまでNN勉強法のメリットや成功例を見てきましたが、注意すべき点やデメリットも押さえておきましょう。万能に見えるNN勉強法ですが、場合によってはリスクや落とし穴もあります。以下に主な注意点をまとめます。
第一志望不合格時のリスクが大きい
NN勉強法最大のデメリットは何と言ってもこれです。志望校一校に絞って勉強するため、万が一その学校に合格できなかった場合のダメージが大きくなります。
他の学校の過去問演習や対策がおろそかになりがちなので、滑り止め校すら受からない…という最悪の事態も起こりかねません。このリスクを下げるために、前述のように秋以降は併願校の対策にも最低限取り組む、模試結果次第では志望校変更も柔軟に検討する、といった臨機応変さが必要です。
「NN勉強法=志望校対策だけやればいい」というわけではなく、自分の合格可能性を客観視しながらバランスを取ることも忘れないでください。
視野が狭くなりがち
小学生の段階で「第一志望とそれ以外」という発想に縛られてしまうことへの懸念も指摘されています。
確かにNN勉強法では志望校を絶対視するあまり、他校や他の選択肢に目が向かなくなる傾向があります。例えば、本来お子さんに合った学校が他にあっても、最初に決めた志望校に固執するあまり見逃してしまうかもしれません。また、「〇〇中に入れなければ敗北だ」という考えが強まりすぎると、受験をチャレンジしない子や他の学校を選ぶ子を無意識のうちに下に見るような態度につながる恐れもあります。
実際、教育評論家の中には「小学生に『入試こそすべて』と思わせてしまうのは良くない」と指摘する声もあります。入試はあくまで通過点であり、本来の目的はその先の良い教育を受けること、大人として成長することです。NN勉強法に取り組む際も、「志望校合格は大事だけれど全てではない」ということを折に触れてお子さんに伝え、広い視野と健全な価値観を失わないよう注意してあげてください。
精神的プレッシャー・負担
NN勉強法は良くも悪くも「背水の陣」の戦略です。一校に絞るからこそ合格可能性は上がりますが、その学校に全力投球するプレッシャーも相当なものです。
特に真面目なお子さんほど、「落ちたらどうしよう…」という不安や重圧を感じるケースがあります。
NNコースでは同じ志望校の仲間がいるため連帯感が生まれやすい一方、仲間がライバルでもあるため競争によるストレスもあります。選抜クラスについていけず自信を失ってしまう子もゼロではありません。家庭でNN勉強法をする場合も、「自分にはこの志望校しかないんだ」「絶対負けられない」と思いつめすぎると精神的に辛くなってしまうかもしれません。
親御さんとしては、お子さんの様子をよく観察し、必要以上にピリピリしすぎていないか気を配ることが大切です。時には気分転換をさせたり、「仮にダメでもまた次があるよ」と声をかけたりして、プレッシャーを緩和するフォローをしてあげましょう。
難関校向けの勉強法である
もともとNN勉強法(NNコース)は開成・麻布・桜蔭・慶應など最難関私立中学の合格を目指す子向けに開発された方法です。これらの学校は入試問題に独特のクセがあり、対策を絞るメリットが大きいからです。
逆に言えば、入試難易度がそこまで高くない学校や、公立一貫校など幅広い基礎力を問う学校を受験する場合には、NN勉強法の優先度は下がります。まずは教科全般の総合力をしっかりつけることの方が合否を分けます。お子さんの志望校のレベル帯や出題傾向を見極め、「この学校ならNN的戦略が有効そうだ」「この学校はまず基礎固めが先だな」と判断しましょう。NN勉強法はあくまで難関校突破の一手段であって、すべての中学受験生にそのまま当てはまるわけではない点に注意が必要です。
すべての子に合うとは限らない
勉強法には向き不向きや相性があります。NN勉強法はハマる子には劇的な効果を発揮しますが、誰にでも万能な方法ではありません。
例えば、ひとつのことに集中するのが苦にならない子や負けず嫌いで競争心が強い子には向いていますが、飽きっぽかったりマイペースなタイプの子にはストレスになる可能性があります。親御さんが「この方法が良さそうだ」と思っても、お子さん本人が燃え上がらなければ成果は出ません。
実際、札幌の学習塾「大成会」のコラムでも「ある人にとって最適な勉強法が、すべての人によい効果をもたらすとは限らない。NN勉強法も丸ごと真似するのではなく、自分に合う要素だけ取り入れるべき」と指摘されています。お子さんの性格や学習スタイルに照らして、「ここは真似しよう、でもここは我が子には合わないかも」という取捨選択をする柔軟さを持ちましょう。
以上が主な注意点・デメリットとなります。大切なのは、NN勉強法を絶対視しすぎないことです。
「すごく効果があるらしい」と聞くと飛びつきたくなりますが、合う合わないやリスクも踏まえた上で、あくまで手段の一つとして冷静に活用するのが賢明です。【うまくいかなければ軌道修正できる】くらいの気持ちで構えていた方が、お子さんものびのび力を発揮できるでしょう。

どんなタイプの子に向いているか?逆に向かないケースは?
NN勉強法がハマりやすいお子さんのタイプと、そうでないケースについて整理してみましょう。
◎ NN勉強法が向いているタイプのお子さん:
- 強い目標意識を持っている子: 「どうしても◯◯中に入りたい!」という憧れや目標がはっきりしている子は、NN勉強法で大きく伸びます。志望校合格を絶対のゴールに据えるため、モチベーション高く努力を継続できるからです。ライバルと競い合う環境にも触発され、「負けたくない」という闘志でさらに頑張れるでしょう。
- 集中力・粘り強さがある子: 一つのことにグッと集中して取り組める子や、多少の困難があっても粘り強く食らいつく子は、長時間の演習や難問揃いの対策にも耐えて成果を出せます。「気づけば何時間も勉強していた」というタイプならNN勉強法のハードな勉強量にも適応しやすいでしょう。
- 競争が励みになる子: 仲間と切磋琢磨することで力を発揮する子にも向いています。NNコースのような選抜環境では周囲もハイレベルです。「負けたくない」「自分も頑張ろう」という良い刺激を受けて伸びるタイプの子には理想的な環境と言えます。逆に競争にストレスを感じない子であることも重要です。
- 難問に興味を持てる子: 志望校対策では難問奇問に挑む場面も多くなります。「パズルみたいで面白い!」と入試問題そのものをゲーム感覚で楽しめるような子は、NN勉強法で力を発揮しやすいです。難しい問題を解くこと自体に喜びを見いだせれば、勉強が苦行ではなくなるでしょう。
△ NN勉強法が難しいかもしれないタイプのお子さん:
- 目標が定まっていない子: 「志望校はなんとなくここにするけど他でもいいや」くらいの温度感だと、NN勉強法のスイッチは入りにくいでしょう。強い目的意識がないまま一点集中の勉強をしても長続きしません。志望校にそこまで執着がない場合は、無理にNN流にこだわらず、複数校併願前提でバランスよく勉強した方が結果的に良いこともあります。
- 基礎学力がまだ安定していない子: 志望校のレベルによりますが、たとえば偏差値帯が中堅以下の学校志望の場合や、そもそも学力が安定していない段階では、NN的な特化勉強よりまず基礎固めが優先です。応用問題ばかり演習して肝心の基本問題を落としては本末転倒です。まずはオーソドックスな学習法で土台を固め、NN法は仕上げ段階で投入するくらいの意識でも遅くありません。
- 長時間勉強に耐えられない子: 体力的・精神的にまだ幼く、1〜2時間の勉強でも集中が切れてしまう子には、NN勉強法のハードさは負担が大きすぎます。無理をさせると勉強自体が嫌いになり逆効果になりかねません。そういう場合は短時間でも内容を濃くしたり、休憩を細かく入れつつ徐々に勉強体力を伸ばす工夫が必要です。一気に詰め込むNN流は適用を待った方がよいでしょう。
- 競争やプレッシャーに弱い子: 神経質で緊張しやすかったり、自分に自信が持てないタイプの子は、NN的な環境で委縮してしまう可能性があります。できる子たちに囲まれて「自分はダメだ」と落ち込んでしまっては逆効果です。そういう場合は無理に特訓クラスに入れず、まずメンタル面を強化したり成功体験を積ませてあげることが先決です。競争心を煽るより、「あなたはあなたのペースで大丈夫」と安心させる方が伸びる子もいます。
このように、お子さんの性格や学力の状況によってNN勉強法の向き不向きがあります。もちろん、人は成長するので「最初は無理と思っていたけど6年生になって集中力がついた」など状況が変わることもあります。その時々でお子さんの様子を見極め、適材適所でNN勉強法を活用するようにしましょう。
無理に型にはめる必要はありません。前述のように、「この部分は良さそうだから取り入れてみよう」「ここはうちの子には合わないから別の方法で補おう」といった柔軟な姿勢でエッセンスを活用するのがおすすめです。

保護者ができるサポートと心構え
NN勉強法を成功させるには、保護者のサポートが欠かせません。親御さんが良きマネージャー・コーチとなってお子さんを支えることで、初めてNN勉強法の効果が最大限発揮されると言っても過言ではありません。以下に、保護者ができる具体的なサポート策と心構えをまとめます。
目標の共有と動機づけ
まずは親子で志望校合格という目標をしっかり共有することが大切です。
お子さんが「何が何でも◯◯中に行きたい!」という気持ちを持てるよう、学校の魅力を話し合ったり、文化祭・説明会に一緒に行ってモチベーションを高めたりしましょう。保護者も「一緒に頑張ろうね」という姿勢で寄り添い、やる気を引き出す声かけを意識します。
ただし、決して無理強いにならないよう注意です。「あなたが行きたいと言ったんだから頑張りなさい!」とプレッシャーをかけすぎると逆効果になりかねません。あくまでお子さん自身の夢を応援する立場で、前向きな動機づけを心がけましょう。
学習計画・進捗の管理
NN勉強法では通常以上に綿密な計画管理が求められます。
塾の宿題、志望校対策、自校の学校生活など両立すべきことが多岐にわたるため、親御さんがスケジュール調整を手伝ってあげると良いでしょう。「今日は塾の宿題を早めに終わらせて夜は過去問演習に充てよう」「土日は模試とNN特訓があるから月曜に振り返り時間を取ろう」といった具合に、全体の学習バランスを見て調整する役割です。
また、勉強の進捗を定期的にチェックし、計画通り進んでいるか、無理が出ていないかを確認します。必要に応じて計画を修正する柔軟さも持ちましょう。親がマネジメントを担うことで、お子さんは勉強そのものに集中しやすくなります。
教材・情報の提供
志望校の過去問集や対策教材、参考書など、必要な教材を揃えるのも保護者の大切な役目です。
前述のように過去問は早めに購入し、お父様お母様が目を通して情報収集しておくとよいでしょう。志望校の入試傾向について、本やネットで調べて得た情報があれば子どもに伝えてあげます。「〇〇中は社会で時事問題がよく出るみたいだからニュースをチェックしようか」などとアドバイスすると効果的です。
また、学校説明会や塾の保護者会にも積極的に参加し、最新情報や他の合格者の体験談を集めてみましょう。それらの情報はきっと学習計画の見直しやモチベーション維持に役立つはずです。親御さんが情報アンテナを張り、お子さんにとっての「ナビゲーター」になってあげてください。
学習環境の整備
長時間の集中した勉強ができるよう、家庭での学習環境を整えることもサポートの一環です。
静かな個室や勉強部屋を用意し、必要な参考書や文具は手の届くところに配置しましょう。リビング学習派の場合も、テレビを消す、家族が協力して静かにするなど配慮します。スマホやゲームなど誘惑になるものは時間を決めて預かるなど工夫しましょう(完全禁止は息抜きの場を奪うので様子を見ながら)。
また、生活リズムの管理も重要です。睡眠不足や体調不良では勉強の効率が下がります。夜更かしせず早起きして朝型で勉強時間を確保する、栄養のある食事を用意する、適度な休息時間を設けるなど、親御さんが健康面・生活面をサポートしてください。
NN勉強法は過酷なマラソンのようなものですから、親が伴走者兼サポーターとして体調管理を支えることが、お子さんのパフォーマンス維持に直結します。
メンタル面の支え
志望校に全力投球する過程では、お子さんも不安になったり落ち込んだりすることがあります。そんな時こそ親御さんの出番です。ポジティブな声かけを常に心がけ、「よく頑張っているね」「少しずつ力がついてきたね」と努力を認めてあげましょう。
結果が出ない時でも叱責や悲観的な発言は避け、「まだ時間はあるから大丈夫、次やってみよう」と励まします。時には気分転換に付き合って一緒に散歩する、好きなおやつを出すなどリラックスさせる工夫も効果的です。
親はつい熱が入りすぎてしまいますが、お子さんにとって家庭は安心できる避難所でなければなりません。「家に帰ればホッとできる」と思えるからこそ、また翌日頑張れるのです。くれぐれも家庭までピリピリしたムードにならないよう、親御さん自身がゆとりを持った接し方をしましょう。
押しつけない姿勢
最後に忘れてはならないのは、「NN勉強法に固執しすぎない」という親の姿勢です。いくら良い方法とはいえ、お子さんに合わないと感じたら柔軟に方向転換する勇気も必要です。
親御さんが「あれほど良いと言われているNN勉強法をやったのに成績が上がらない、子どもの努力が足りないのでは」などと考えてしまうと、お子さんにもそのプレッシャーが伝わってしまいます。
大事なのは自分なりのアレンジです。親御さんも常に批判的精神を持ち、「うちの場合はここを変えてみよう」「別のやり方も試そう」と冷静に判断してください。NN勉強法は手段の一つに過ぎず、お子さんの将来は入試だけで決まるわけではありません。広い視野を持って、お子さんに最適なサポートを選択していきましょう。
以上、保護者ができるサポートを挙げましたが、一番大切なのは「お子さんを信じてあげる」ことかもしれません。たとえ途中で模試の判定が悪かったりスランプがあっても、最後まで信じて伴走してくれたご両親に感謝している合格者の声はとても多いです。NN勉強法にチャレンジするなら、親子二人三脚で乗り越える覚悟を持ち、お子さんの頑張りを支えてあげてください。

まとめ:NN勉強法を上手に取り入れて志望校合格へ
最後に、本記事のポイントを整理しつつ、NN勉強法の導入を検討しているご家庭へのメッセージをお送りします。
NN勉強法とは、志望校の傾向を徹底的に研究し「何が何でも合格する」という強い意志で勉強し抜く方法でした。早稲田アカデミーのNNコースに端を発し、芦田愛菜さんの合格体験で一躍注目されたこの勉強法は、短期間でも効率よく第一志望合格の可能性を引き上げられる合理的な手法です。難関校受験生にとっては強力な武器となり得る一方で、他校対策が手薄になるリスクや精神的プレッシャーも伴う諸刃の剣でもあります。
NN勉強法を取り入れる際は、メリット・デメリットを踏まえつつお子さんに合った形でアレンジすることが成功のカギです。志望校への想いが強く集中力のあるお子さんには大きな効果を発揮しますが、そうでない場合は無理に真似する必要はありません。
例えば、志望校の過去問分析というエッセンスだけ活用するとか、夏休み~入試直前の期間だけNN式に専念してみる、といった部分的な導入でも十分意味はあります。「自分流にカスタマイズしてこそ成果が出る」という意識で、いいとこ取りをしていきましょう。
保護者の皆さんへのお願いとしては、どうかお子さんの挑戦を温かく支えてあげてください。NN勉強法はお子さんにとって大変なチャレンジですが、親御さんの励ましとサポート次第で乗り越えられる壁もあります。情報提供・環境整備・メンタルケアなどできることをしつつ、時には肩の力を抜いて「最善は尽くしたんだから大丈夫」と笑顔で言ってあげる余裕も持ちたいですね。
中学受験はゴールではなくスタートです。NN勉強法で培った集中力や粘り強さ、そして「何が何でもやり遂げるんだ!」という経験は、合否に関わらずお子さんの大きな財産となるでしょう。【努力はきっと報われる】と信じて、ぜひ前向きにNN勉強法の導入を検討してみてください。適切に活用すれば、きっと志望校合格という夢に一歩近づけるはずです。
皆さんの健闘をお祈りしています!まずはできる範囲でNN勉強法を取り入れ、志望校合格に向けて親子で二人三脚の受験勉強を進めていきましょう。応援しています!




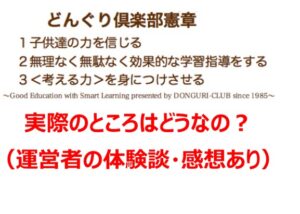
コメント