中学受験は、多くの家庭にとって大きな決断です。特に、受験科目を4科目にするか、それとも2科目に絞るべきかという悩みは尽きません。お子さんの負担を考えて2科目受験を検討しつつも、「本当に有利なの?」「志望校の選択肢は狭まらない?」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、中学受験の2科目入試について、メリット・デメリットから、4科目受験との違い、最適な戦略まで、プロの視点から徹底的に解説します。この記事を読めば、お子さんにぴったりの受験方法がきっと見つかります。
中学入試の多様な入試科目にはどんな種類がある?
中学受験の入試科目は、国語、算数、理科、社会の4科目が主流です。
しかし近年では、お子さんの負担軽減や、特定の能力を持つ生徒を確保したいという学校側の意図から、入試の多様化が進んでいます。2025年度には、多くの学校で4科目入試が基本となっており、午後入試を中心に国語と算数の2科目で受験できる学校が増加しています。
そのほかにも、算数1科目入試や、英語を入試科目に取り入れる学校、さらには公立中高一貫校で採用されている適性検査型入試を導入する私立校も出てきました。例えば、日本大学豊山女子中学校は2026年度から算数・国語1科目入試の導入を発表しています。このように、中学入試の選択肢は増えており、志望校の入試科目をしっかり確認することが重要です。
2科目入試のメリット・デメリットを徹底比較
2科目入試には、主に以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 勉強の負担が軽減される: 理科と社会の勉強時間がなくなるため、お子さんの学習負担が軽くなり、体力面・精神面での余裕が生まれます。
- 得意科目に集中できる: 苦手な理科や社会に時間を割く必要がなくなり、国語と算数という主要科目に集中して対策できます。
- 併願校の選択肢が増える: 午後入試で2科目入試を実施している学校が多く、午前中に4科目入試の学校を受験した後、午後にもう1校受験するといった戦略的な受験が可能です。
デメリット
- 選択肢が少なくなる: 依然として4科目入試が主流のため、最初から2科目に絞ってしまうと受験できる学校の選択肢が大幅に狭まります。
- 1科目の失敗が命取りになる: 4科目入試であれば、1科目で失敗しても他の3科目でカバーできる可能性がありますが、2科目入試では国語か算数のどちらかで失敗すると、リカバリーが難しくなります。
- 入学後の学習で苦労する可能性: 中学入試の理科・社会は、中学入学後の学習内容の基礎となる知識が詰まっています。中学入試で理科・社会の勉強をしないまま入学すると、周りの4科目受験生に比べて知識不足となり、入学後に苦労するケースも少なくありません。

行きたい学校を1校に絞って勉強していたから、2科目受験というのがあることすら知りませんでした。
塾に行ったり、複数の学校を考えていれば、このような情報も入ってきたのかもしれないですが。
うちの子どもは短期間(約1年間)で4科目を勉強していたので、さすがにキャパオーバーになっていましたが、確かに2科目受験できる学校も視野に入れて勉強する場合には、その道もありますね。
4科目 vs 2科目|どっちが有利?
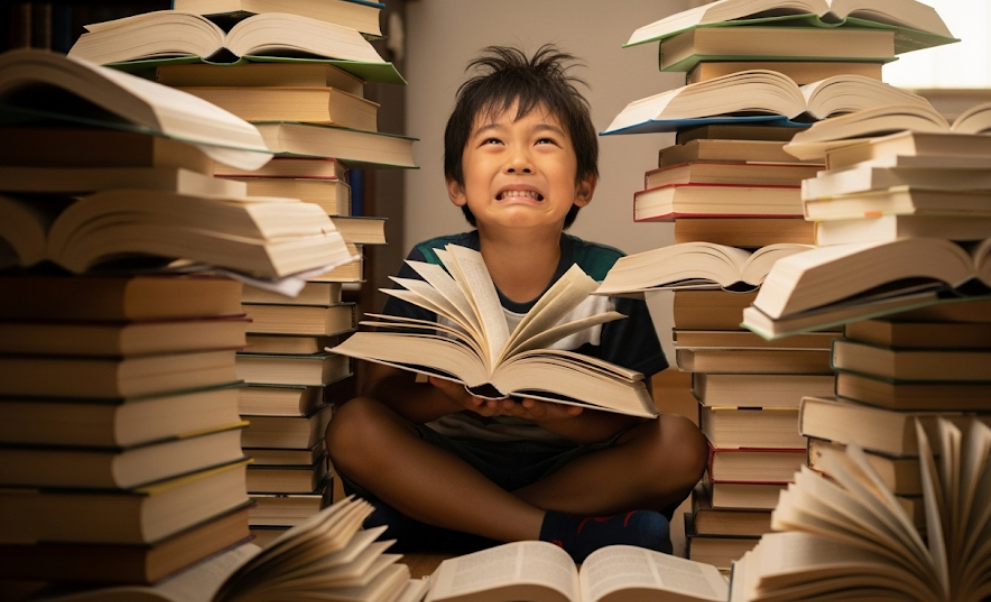
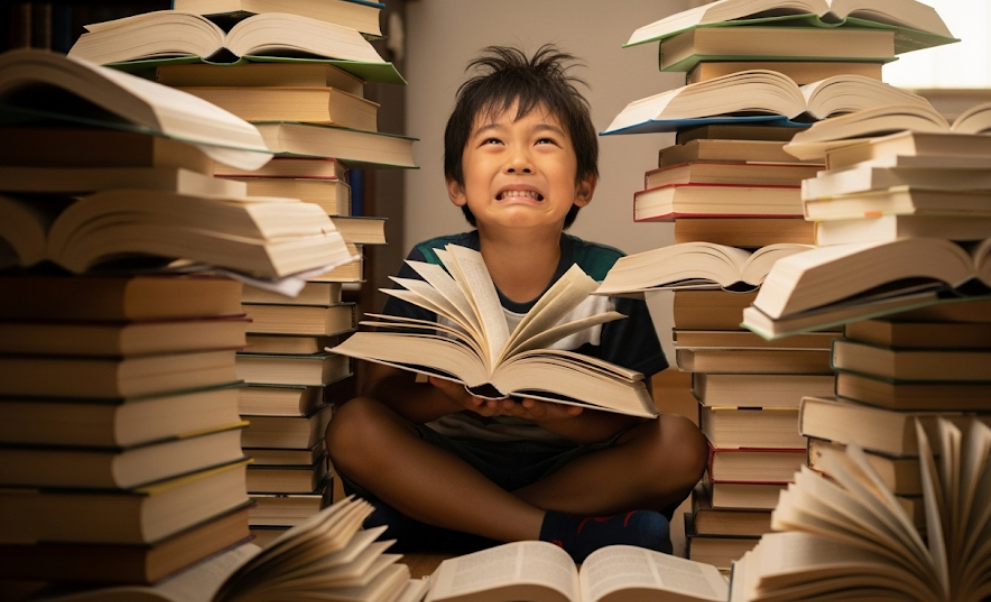
「4科目の方が有利」と言われるのはなぜ?
中学受験では、一般的に「4科目受験の方が有利」と広く言われています。
その最大の理由は、合格のチャンスが2回あるからです。
多くの学校が4科目と2科目の両方を実施している場合、まず国語と算数の合計点で合格者の大半(例えば7~8割)を選抜します。その後、残りの合格者を理科と社会を含めた4科目の合計点で選抜するのが一般的です。2科目受験を選択した場合、この2回目の選抜には進めません。つまり、合格のチャンスが1回しかないことになります。
また、ある塾の卒業生の対談では、4科目受験生は中学受験の勉強を通して、社会や理科でも一定の知識レベルを身につけていることが指摘されています。これは、将来的な学びの土台となり、教養を身につける上で非常に有益であると考えられています。
2科目入試は「敗者復活」がないって本当?
先述の通り、多くの学校では合格者を選抜する際に、まず2科目(国語と算数)の合計点で合否を判定し、次に4科目(国語、算数、理科、社会)の合計点で再度合否を判定するという2段階方式を採用しています。この場合、2科目受験をした生徒は、最初の段階で合格基準に達しなければ、理科と社会で点数を挽回する「敗者復活戦」に進むことができません。
2科目入試は、国語と算数だけで勝負を決めなければならないため、まさに「背水の陣」と言えます。特に、国語や算数に苦手意識があるお子さんにとっては、よりプレッシャーの大きな受験になるでしょう。
2科目に絞るべきではないケースとは?
以下のケースに当てはまる場合、安易に2科目に絞ることはおすすめできません。
- 受験校の選択肢を広げたい場合: ほとんどの学校が4科目入試を基本としているため、早い段階で2科目に絞ると志望校の幅が大きく制限されてしまいます。
- 御三家など偏差値上位校を目指す場合: 偏差値50以上の難関校のほとんどは4科目入試のみで、2科目受験の選択肢はありません。
- 国語と算数が苦手な場合: 2科目入試は、国語と算数が得意な子たちが集まるため、この2科目が苦手なお子さんにとっては厳しい戦いになります。
2科目受験が向いているのはどんな子?
2科目受験は「そのご家庭の置かれている状況」によって判断が変わるとされています。以下の条件に当てはまるお子さんは、2科目受験が向いている可能性があります。
- 受験勉強のスタートが遅かった: 例えば、6年生から中学受験の勉強を始めた場合など、時間が足りないケース。
- 特定の科目が苦手: 4科目の中で理科や社会が極端に苦手で、学習のモチベーションが保てない場合。
- 志望校がもともと2科目入試である: 行きたい学校がもともと2科目入試をメインにしている場合。
- 習い事との両立を重視したい場合: 勉強の負担を減らし、他の活動に時間を割きたいと考える場合。



まさにうちの子どものように、受験勉強のスタートが遅い場合には、戦略的に2科目受験を目指すのは有効な気がします。1年で4科目を勉強し、かつ、周りに追いついていくのは、よほどもともとの実力がある子以外は難しいと感じます。
2科目受験の最適な戦略|合格への道筋
いつから2科目対策に絞るのがベスト?
中学受験の勉強を始める小学4年生や5年生の段階で、最初から2科目に絞ることはおすすめできません。この時期は、入学後の学習の土台を築くためにも、4科目すべてをバランス良く学習することが大切です。
2科目への絞り込みは、成績や志望校の状況が明確になってくる6年生の夏以降に検討するのが良いでしょう。
4科目をベースに戦略的に活用する具体的な方法
中学受験を成功させるための王道は、やはり4科目を軸に勉強を進めることです。その上で、以下のように2科目受験を戦略的に活用しましょう。
- 午後入試での活用: 午前中に第一志望の4科目入試を受験し、午後に2科目入試を実施している併願校を受験する。
- 得意科目で挑戦する: 4科目の中で特に国語と算数が得意な場合は、特定の学校の2科目入試に絞って挑戦する。
- 学習時間の確保: 算数と国語は学習成果が出るまでに時間がかかるため、6年生の夏以降は理科と社会の勉強を最小限に抑え、国語と算数に時間を集中させる。
中学入学後の「理社」の遅れはどうカバーする?
中学入試で理科・社会を勉強しないまま入学すると、入学後の授業についていくのが大変になる可能性があります。なぜなら、中学入試で学ぶ理科・社会の知識は、中学で学ぶ内容の約6~8割に相当すると言われるほど、深い知識を問われるからです。
この遅れをカバーするためには、中学入学までの期間に、中学入試で学習する範囲の理科と社会を自主的に復習することが大切です。また、日頃からニュースやドキュメンタリー番組などを見て、社会の知識を身につけたり、科学館などに行って理科への興味関心を高めたりすることも有効です。


2科目受験ができる中学一覧と偏差値
【東京/関東】2科目入試を実施している中学は?
東京都内や関東圏では、2科目入試を実施している学校が多数あります。特に、午後入試を導入している学校に多い傾向です。例えば、明治大学附属世田谷中学校は2024年度入試で2科目受験を廃止しましたが、他にも多くの学校が2科目入試を実施しています。ただし、年度によって入試方式が変更されることもあるため、必ず最新の募集要項を確認するようにしましょう。
女子校・男子校・共学の学校例
2科目入試は女子校に多い傾向がありますが、男子校や共学の学校でも実施されています。例えば、男子校では立教池袋中学校、女子校では香蘭女学校(2024年度入試より2科目入試の選択ができなくなりました)、東京女学館中学校、共学では法政大学中学校などがあります。



なるほど、女子高に多いのですね。
2科目入試の偏差値はどのくらい?
2科目入試を実施している学校の偏差値は、多岐にわたります。首都圏模試のデータによると、偏差値50未満の学校では2科目入試が主流であり、2科4科選択制の学校がほとんどです。
一方、偏差値50以上の学校では、4科目入試が圧倒的に多いという結果が出ています。2科目入試は併願校として上位層の受験生が集まりやすいため、高倍率になる傾向があります。


塾・家庭教師の視点から見る2科目受験
多くの塾が4科目を推奨する理由
多くの大手塾やプロの講師は、中学受験では4科目を推奨しています。
その理由としては、第一に受験校の選択肢を広げるためです。4科目対策をしておけば、2科目入試の学校にも対応できるため、受験戦略の幅が広がります。
また、小学6年生から中学受験を始めた子を除けば、中学受験の勉強は長期戦です。算数と国語だけを毎日やり続けるのは、子供にとって精神的に厳しいものです。理科や社会を適度に入れることで、気分転換になり、学習のサイクルがうまく回るという側面もあります。
2科目受験に特化した塾を選ぶ際のポイント
2科目受験に特化した塾を探す際は、以下のポイントに注目しましょう。
- 国語と算数に特化したカリキュラム: 国語と算数に特化しているため、苦手な単元を徹底的に克服できるか。
- 個別指導の有無: お子さんの理解度に合わせて指導してくれる、個別指導の体制が整っているか。
- 志望校の入試傾向対策: 志望校の入試傾向に合わせた具体的な対策をしてくれるか。
塾によっては、受験生を指導する上で、2科目入試に絞ることを前向きに捉え、その子に合った最適な学習プランを提案してくれるところもあります。



いずれにしても国語と算数がやはり勉強の軸になりますね。
中学受験:2科目か4科目か?
データに基づいた戦略的選択のためのインフォグラフィック。お子様に最適な受験スタイルを見つけましょう。
入試形態の多様化
近年の中学受験は、従来の4科目(国語・算数・理科・社会)入試だけでなく、2科目入試や1科目入試、適性検査型など、多様な選択肢が登場しています。特にお子様の負担を考慮し、2科目受験を検討するご家庭が増えています。
主流は4科目入試
依然として、ほとんどの私立中学校で基本となる入試形態です。選択肢の広さが最大の利点です。
増加する2科目入試
特に午後入試で多く採用され、併願戦略の要となっています。国語と算数が基本です。
新タイプ入試
算数1科目、英語、適性検査型など、学校の特色を反映した入試も増えています。
2科目 vs 4科目:どちらが有利?
偏差値帯で見る入試科目の割合
首都圏模試のデータによると、偏差値50を境に入試科目の主流が大きく変わります。偏差値50以上の学校では4科目入試が圧倒的に多く、選択肢を広く持つためには4科目の学習が基本となります。一方、偏差値50未満の学校では2科目選択可能な学校が大半を占めます。
合格判定の仕組み:「敗者復活」の有無
4科目と2科目の選択が可能な学校では、一般的に2段階で合格者が決定されます。この仕組みが「4科目有利」と言われる大きな理由です。
第1段階
国語・算数の
合計点で判定
(合格者の約7-8割)
第2段階
4科目の合計点で
残りの合格者を判定
(2科目受験生は対象外)
2科目受験生は第1段階のチャンスしかありませんが、4科目受験生は2回のチャンスがあります。これが「敗者復活」の有無であり、4科目受験の大きなアドバンテージです。
メリット・デメリットの比較
2科目受験のメリット
- ✔学習負担が軽く、習い事などとの両立がしやすい。
- ✔国語・算数の得意科目に集中して対策できる。
- ✔午後入試を活用し、1日に複数校受験する戦略が立てやすい。
2科目受験のデメリット
- ✖受験できる学校の選択肢が大幅に狭まる。
- ✖1科目の失敗が合否に直結し、挽回が難しい。
- ✖入学後、理科・社会の知識不足で苦労する可能性がある。
戦略的な科目選択
誰が2科目受験に向いているか?
2科目受験は、すべてのお子様に最適な選択とは限りません。受験勉強の開始時期、得意・不得意科目、志望校の特性などを総合的に判断することが重要です。このチャートは、どのような場合に2科目受験が有効な選択肢となりうるかを示しています。
基本戦略は4科目をベースに考え、6年生の夏以降に状況を見て、2科目受験を併願戦略として活用するのが最も効果的です。

コメント